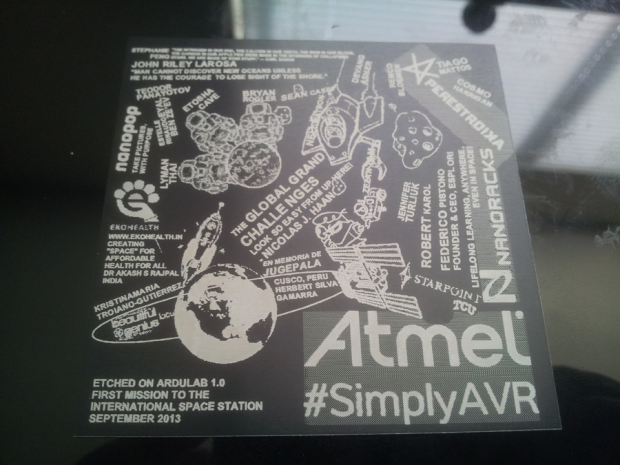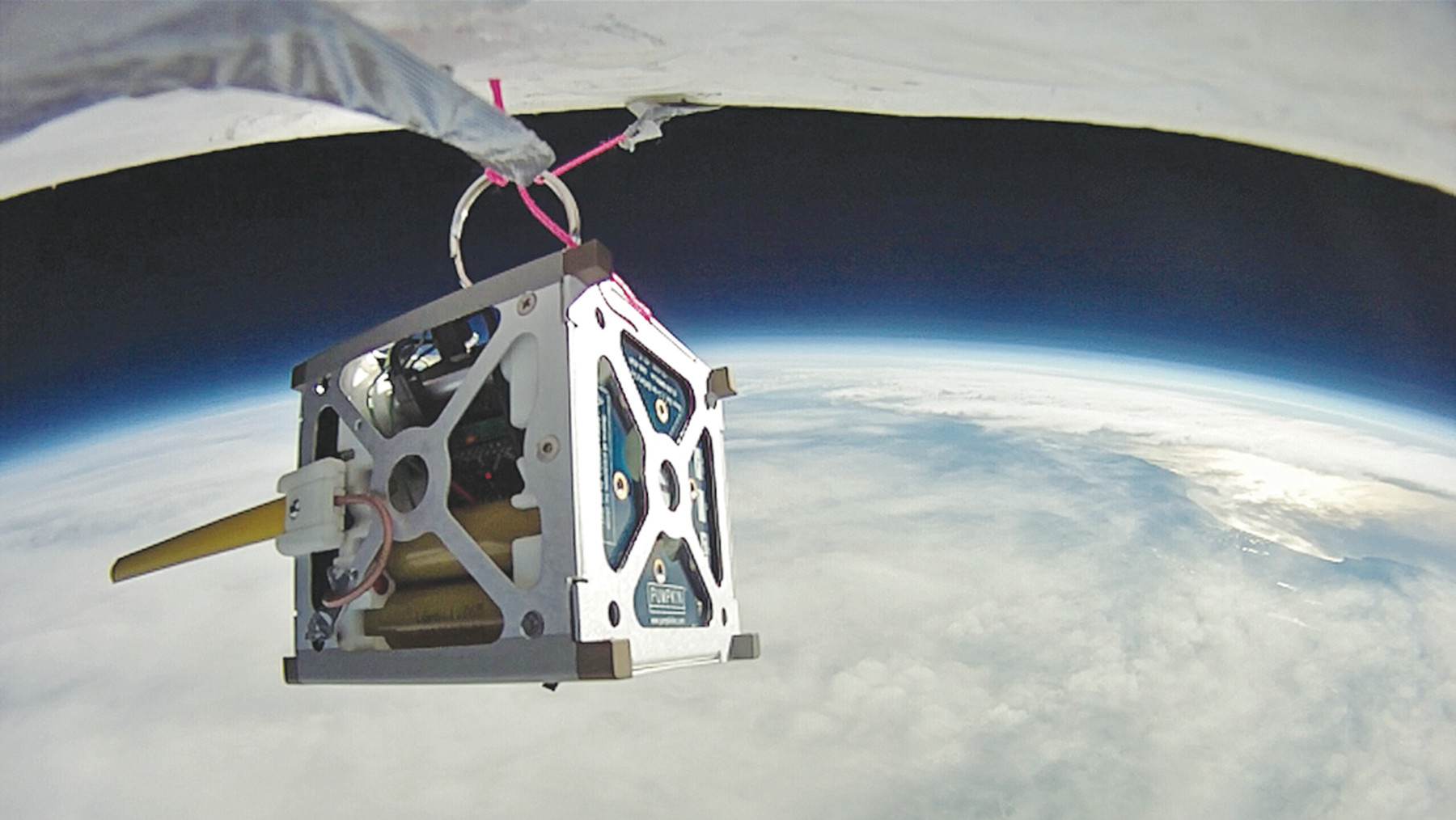2012.05.25
3DプリンタをCTスキャンの解析や宇宙教育に応用しよう
ブラウン大学で生態系および進化生物学部の助教授を務めている神経科学者のSeth Horowitzは、同時にMakerであり、熱烈的な3Dプリンタ愛好家だ。彼は、新しい研究方法も含む、3Dプリンタの活用法に関するレポートをたくさん発表している。
3年前、私は興味深い問題に突き当たった。ある実験の目的で、生きたコウモリの体を苦痛を与えずに拘束し、かつ噛みついたり頭を動かしたりできないようにする器具が必要になったのだ。過去には、アクリル板で複雑な装置を作れる技術者たちと檻のような装置を開発した。それはうまく使えていたのだが、問題は、体の大きさや種類の違うコウモリには、それぞれにあつらえなければならない点だった。ひとつ作るのに数週間かかり、費用は1台数千ドルもした。
しかし最近は、3Dプリンタのキットがウェブ上でも普通に語られるようになってきたので、生きたコウモリの体を拘束する装置を3Dプリンタで作れるかどうか、私も試してみようと考えた。そこで、NASAのRhode Island Space Grantに小規模な実験用助成金を申し込み(暗闇の複雑な空間を飛行できるコウモリはNASAにとっても格好の研究テーマだ)、Makerbot Cupcakeを購入した。
数カ月間、構築し、組み立て、分解し、悪態をつき、再設計し、ようやくコウモリホルダーをプリントできた。材料に使ったプラスティックの代金は50セントほどだ。プリントにはたっぷり2時間かかった。しかし、コウモリホルダーなんて、そういくつもいるものじゃない。私のCupcakeを、もっと活用する方法はないかと考えた。そして気がついたのは、3Dプリントは「データ実現化」の新しい形ではないかと。オブジェクトの形状を定義する単純化された数値からそのオブジェクトを再現するというものだ。遺伝子がタンパク質を作るのと、物理的には同じことだ。身の回りに3Dデータは山ほどある。だからその可能性は無限だ。
少なくともこの10年間、科学と工学の分野では、3Dモデルと三次元画像はごく当たり前のものになっている。CTスキャンから骨や固い組織の三次元映像が作られるようになり、柔らかい組織もMRIでできるようになった。軌道上のさまざまな角度から撮影して得られたデータを使って、地球や月の三次元の地形モデルが再構築して、その中を自由に飛び回れるようにもなった。しかし、これらには本質的な限界がある。画像の中の個々の要素は、見たいと思う部分をよく見えるようにするために、実質的なフィルターがかけられる。そのため、見る人の興味のない部分は隠されてしまうのだ。重なって陰になる部分は、細かい構造が見えにくい。外側は非常に精細に表示されるものの、詳しい内部構造は、視点を変えるだけではなかなか見えないものだ。そして、最大の制約は、あくまで画像だということだ。どんなに美しく、どんなに詳細に作られた画像でも、複雑な物体の情報の中の、視覚情報だけに限定してしまっている。しかしその三次元画像を、物理的な物体として再現できたらどうだろう。もちろん視覚的に確認もできるが、触覚という極めて優れた感覚を使って詳細を感じ取れるようになるだろう。

図1 大人のウシガエルの骨格の変形部分を写した CT スキャン画像。
私は、昔に行った研究のデータを検証するという応用法を思いついた。おもに、ウシガエルを使った聴覚の発達に関する研究だ。ウシガエルは、人間の聴覚研究にとって、次の点で非常に面白い検体となる。第一に、低音域(2500Hz以下)での彼らの聞こえ方が人間とよく似ているということ。第二に、彼らの脳が人間のものよりも弾性があり柔軟であるということ。たとえば、カエルは、中枢神経に損傷を受けても再生ができる。この能力が人間にあれば、雑音性難聴も治療可能になる。しかし、カエルはその可塑性の代償として、環境有害物質や環境条件によるダメージを受けやすくなっている。
2004年、カエルの声を録音しにいったとき、研究員のひとりが奇形のオスの大人のウシガエルを見つけた。耳が片方しかないのだ。それ以外の部分は健康そうに見えた。カエルは、その社会的活動において聴覚の依存が大きいので、こいつは子孫の繁殖や縄張りの確保が難しいはずだ。私たちはそのカエルを捕獲してCTスキャンにかけ、その奇形の度合いを確かめた。CTスキャンは、X線をらせん状に連続照射して対象部分の骨や固い組織の三次元画像を撮影するという装置だ。そのカエルのCTスキャン画像(図1)から、両方の内耳は正常ながら、片方は鼓膜と、アブミ骨と呼ばれる鼓膜と内耳をつなぐ小さな軟骨が欠損していることがわかった。

図2 CTスキャンデータを3Dプリントしたところ。
同じ奇形を持つもう1匹のカエルを捕獲して、私たちは、ここで何かが起きていると気づき始めた。この2匹のカエルには外傷の跡がない。発育の途中で何かがあったに違いないのだ。CT画像から、内耳に異常がないことはわかっているので、私たちはこれを、人間の外耳道閉鎖症に似た症状だと判断した。内耳は正常だが、外耳と中耳に先天性異常が起きるというものだ。それから数年が経った今、再びその画像を確かめてみた。今度は3Dプリンタの力を借りてだ。問題の箇所のCTの元データを、オープンソースソフトウェアのImageJを使って3Dプリンタ対応のステレオリソグラフ・ファイルに変換し、25倍に拡大してプリントした(図2)。
モデルを手にして、ひっくり返したり触ったりしてみると、内耳の聴神経(第8脳神経)が脳とつながる部分が明らかに左右非対称になっていることがわかった。つまり、この奇形は外耳道閉鎖症によるものではない。むしろ、農薬が紫外線によって変化してできた催奇形物質を、成長のある段階で浴びたことによる奇形と考えるべきだ。3Dプリンタでモデルを製作したことで、オリジナルのデータをコンピュータの画面で見たいたときよりも、奇形の原因に関して、ずっと深い観察力が得られたというわけだ。物理的な三次元モデルを作れば、手と目という、私たち持っている2つのツールを同時に使って、ハードやソフトに大金をつぎ込むよりも、ずっと大きな発見ができるようになるのだ。
私がもうひとつ興味を持っていることに宇宙教育活動がある。これにも3Dプリンタを活用しようと考えた。地球を含む宇宙の探索は、20世紀から21世紀にかけて、人類にとってもっともエキサイティングな冒険だ。しかし、その興奮は画像を通してしか味わえない。質量や塩分分布がわかる地球儀、火星の渓谷や木星の衛星エウロパの地割れを飛行する3Dフライスルー、月のクレーターの高解像度映像など、一部の例外を除いてすべては視覚だけの世界だ。もし、小惑星の模型を特注で作らせるしたら、何千ドルもかかってしまうだろう。山の尾根や陸塊の形が手で触ってわかるように立体的に作られた地球儀や地図は何百年も前からあるが、基本的に目の不自由な人のために作られたもので、学校教材としてわずかに作られているだけだ。それで、3700万人の全盲の人たちに、どうやって宇宙のことを教えたらいいのだろう。1億2400万人の視覚障害者も言うに及ばずだ。さらに言うなら、目の見えるさらに多くの人たちで、小惑星の模型を触れない人たちにはどうしたらいいのだろう。
2010年、私は小惑星の三次元データを使って、天体や地形の3Dプリントする方法を探り始めた。小惑星のデータは、レーダーデータ(ワシントン州立大学電気工学学部のScott Hudson 教授のレーダー研究によるもの)や、アリゾナ大学のHiRISEグループによる火星のデジタル地形データなど、たくさん公開されている。そのうちいくつかは、Celestiaなどの宇宙シミュレーションプログラムで使われている。私は、これらのNASAから公開されているデータを(苦労して)ステレオリソグラフ・ファイルに変換し、小惑星、火星の月「フォボス」と「ダイモス」、それに火星のクレーター「グーセフ」などの惑星地形の三次元モデルをプリントした(図3)。

図3 小さな天体の画像(上)と3Dプリントしたもの(下)。
しかし、オンラインソフトウェアが新しい教育の形や物作りに影響を与える速度を知らしめたくて、私は小惑星「ベスタ」のモデルを作ってNASAを出し抜いた。ベスタは小惑星帯の中で2番目に大きな小惑星で、他の小惑星や天体とは異なる特徴を持っている。ベスタを選んだのは、「エロス」などのジャガイモ型小惑星との違いを知ってもらうためだ。これを握れば、石の塊と惑星の間の、重力の大きさによる形状の違いを即座に感じ取ることができる。
ベスタには、現在、探査機ドーンが軌道を周回していて、何万枚もの美しい写真を送ってきている。しかし、NASAはまだ、その公式な3Dモデルは発表していない。私は2つの方法を使ってこれを実現した。ひとつは、ベスタの回転画像をフリーのオンライン3Dモデリングソフト(www.my3dscanner.com)に取り込んで基本のポイントクラウドを作った。形状は、連続写真で明るさが共通する地点から割り出した。それらのデータをディテール用に使い、公開されているベスタの「グローバルマップ」と結合させて、軌道から撮影された写真を元に作った玉子型を平面に展開したところへマッピングした。こうして、低解像度ながら実際の3Dモデルを、NASAよりも早く作ることができたのだ(図4)。

図4 小惑星ベスタ – 左が探査機ドーンからの画像。右が私が作った 3D プリント版。
私はなにも、NASAを出し抜いたことを自慢したいわけではない。無料で公開されている豊富なツールやデータを使えば、すごいことができるという手本を示したかったのだ。画像から3Dモデルを作ってプリントすれば、自分で宇宙のスケールモデルが作れてしまう。目の見えない子供たちに、大西洋の真ん中の海溝を感じさせたり、シャープな月のクレーターと風で浸食された火星のクレーターの違いを教えることもできる。職業レベルでは、探査車両などのテスト用に正確な地形モデルなどを作ることで、幅広い人たちの宇宙探査への興味をつなげることができる。そして、視覚障害のあるなしに関わらず、新しい世代の子供たちには、宇宙は自分の手で握ることができるのだと教えることができるのだ。
– Seth Horowitz
[原文]