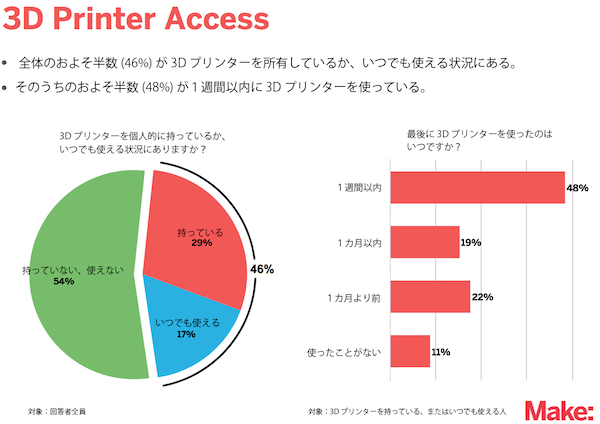本記事は、久保田晃弘さん(多摩美術大学情報デザイン学科 教授)に寄稿していただきました。
『ラインズ―線の文化史』『メイキング―人類学・考古学・芸術・建築』『ライフ・オブ・ラインズ―線の生態人類学』といった著作が、ここ数年続けて邦訳されたティム・インゴルドは、1948年英国生まれの人類学者である。「メイキング」という本のタイトルだけで、なにやらメイカームーブメントとの繋がりを感じさせてくれるが、これは本の最初のタイトル案であった「4つのA(人類学、考古学、芸術、建築)」が、いずれも「つくること」を通じて思考する方法であるところからつけられたものだ。インゴルドは「思考を通じてつくること」と「つくることを通じて思考すること」は全く異なるという。同様に「思考を通じて文章を書くこと」と「文書を書くことを通じて思考すること」も異なる。この連載は僕自身にとって、この「文章を書くことを通じて思考すること」に他ならない。ものをつくることと、文章を書くことはとても似ている。つくることも書くことも「作者と素材のあいだの相互作用(コレスポンダンス)」であり「成長のプロセスとも一致する」ものなのだ(『メイキング』9ページ)。
そんなインゴルドの日本語における最新刊は、今年の3月に出版された『人類学とは何か(Anthropology: Why It Matters)』である(原書は2018年)。「私たちはどのように生きるべきか?(How should we live?)」という問いから始まるこの本は、人類学を「世界中に住まうすべての人の知恵と経験を、どのように生きるのかというこの問いに注ぎ込む」ものだと唱える。人類学者が求めているのは、客観的な知識ではなく、知恵であり、その根源にあるのは、「私たちが知っている世界はどのようにあるのか」という存在論的な問いである。その姿勢は前回の存在論的なデザインとも深く通じている。
インゴルドは2018年3月28日にイタリア、トリノの市民ギャラリーで「芸術、科学そして研究の意味(Art, Science and the Meaning of Research)」というタイトルの公開講座を行った。この時のテキスト、そしてそれをさらにブラッシュアップしたものが、ウェブで公開されている。講演のベースにある問題意識は、「人類学者にとって研究とは何か」である。科学者にとっての研究とは通常、ある管理された条件の下でデータを収集・分析して仮説を検証し、推測と反論を通して理論を前進させることを指している。そうすることで、科学者たちは客観的な知識を収集、生産し、それを人や時代を超えて積み重ねていく。こうした専門的な研究は、確かに研究のひとつの形態であり、しかも科学者はそれを研究のデフォルトだと思っている。しかし研究の本来の目的は、知識の生産ではなく、真理の探究にある(The proper purpose of research lies in the pursuit of truth.)。
「私たちはどのように生きるべきか」を問う人類学の研究とは、
・自分たちの研究の行き着く先を事前に知ることができない
・研究が行われる条件が自分たちの手に負えないものである
・研究が実際に結論に達することがない
ようなものである。こうした研究は人類学だけでなく、科学以外の学問のほとんどにとっても同じだろう。科学というのは、あるひとつの方法論であり、管理された観測データにもとづく理論的考察によって得られた法則が、それを観測した状況を超えて通用することを仮定して進めていく経験則(だれもこの仮定が成立することを証明できない)である[1]。インゴルドは、こうした科学の研究を「芸術の」研究と対置させる。
But that research is what the scientist does is not in question. With artists, however, it is precisely the opposite. It would have been unusual, in the past, for artists to admit to carrying out research, and even more unusual for the public to recognise it as such. Nowadays however, for a variety of reasons more and more artists present what they are doing as research. And this leaves the public puzzled.
(しかし、研究が科学者がやるものであることに疑問を持つ人はいません。しかしアーティストにとっては、まさにその逆です。これまで、アーティストが研究を行っているのを認めるのは珍しく、一般の人々がそのことを認めるのはさらに珍しかったでしょう。しかし最近では、様々な理由から、自分たちがやっていることを研究として発表するアーティストが増えてきています。そのため、一般の人々は困惑しています。)
インゴルドの講演の目的は、一般的な研究に対する考え方をひっくり返すことにあった。インゴルドは「研究は基本的には芸術の実践である(In brief, I shall argue that research is fundamentally a practice of art.」と主張する。自分たちが行っていることが、本当に研究なのかどうかを科学(者)は証明できない。しかし研究のデフォルトをリセットして、科学者がもう少しアーティストの例に倣うようにすれば、つまり科学のルーブリック(指示)の下での芸術的研究ではなく、芸術のルーブリックの下での科学的研究を行えば、私たちは現在の世界が切実に必要としている、科学と芸術の適切な統合に必要なバランスを回復し、それらの融合に向けた第一歩となるはずだ。
ここでインゴルドはユニークな、しかしこの問題の核心に迫る喩えを登場させる。研究する人を広義の「探検家(explorers)」とした時に、科学的な研究者はいわば「登山家(mountaineer)」のようなものである。登山家にとって重要なのは、最初に山に登ることであり、一旦誰かが登った山に再び登ることは、確認以上の意味はない。しかし「丘歩き(hillwalker)」にとって、たとえすでに登ったことがある山でも、その登山の風景は不変のものではない。それどころか、風景は常に変化していて、そんな刻々と変化する風景の中を歩く人にとって「一度登った山は不変のものであり、2度と登る必要はない」という考えは、逆に不条理でしかない。
文字通りの意味で、研究(research)とは探索を再び行う(re-search)行為である。再度探索するということは、以前に行ったことを、まったく同じ条件で繰り返すことではない。ある探索と別の探索の間には、常に差異がある。それは、同じ道を何度も何度も歩いたり、同じ丘を幾度となく登ったりするようなものである。どんな歩き方も、どんな登り方も、前に行ったものと同じにはならない。一歩一歩が新しい始まりになる。芸術の研究とは、つまりは丘歩きのような登り方のことである。研究者は登山家になる必要はないし、研究者は科学者のふりをする必要もない。なぜなら、これまで私たちが幾度となく経験してきたように、山は常に変化していて、2度と同じ状態になることはないからだ。だからこそ私たちは、山に登ることに対する飽くなき欲望に駆り立てられて、止むことなく進み続ける。そうした行為を私たちは「好奇心」と呼ぶ。研究を駆動しているのは、登山家としての成果や達成ではなく、賞や名誉でもなく、それを行うのに必要な予算でもなく、この好奇心である。
Research, then, is not a technical operation, a particular thing you do in life, for so many hours each day. It is rather a way of living curiously – that is, with care and attention.
(研究とは、人生の中で毎日何時間もかけて行う特殊な出来事、技術的な活動ではありません。それはむしろ、関心と気づきによる好奇心を持って生きていくための方法なのです。)
丘歩きが、そしてアーティストが行っている真理の追求としての研究は、イノベーションのような功利的なものとは何の関係もない。むしろそれは、多くの人が、趣味、おたく、自己満足、物好きなどと呼んでいるようなことに近いかもしれない。しかし、真理が事実を超えたところにあるとすれば、私たちは山の上にいるのではなく、山に包まれているだけだ。研究、知ること、存在することも同様に、それは世界に参加することであり、川のように、山のように、そして生命のように、その最終的な目的地もない。
こうしたインゴルドの研究や探究に関する考え方は、去年オライリー・ジャパンから出版し、監訳を担当した『世界チャンピオンの紙飛行機ブック』の著者のジョン・コリンズ(紙飛行機の飛距離のギネス記録 69.14m を持つ)の実践=生き方を思い起こさせる。
私は大学で航空学を学んだわけではありません。ただ博士なみの好奇心があるだけです。考えようによっては、「よくわかっていない」という答は、冒険の余地があるということです。少なくとも、本書で紹介する紙飛行機に関しては、そういえるでしょう。(p.14)
まず知っておくべきは、科学はすべて、いろいろな現象の理由を、うまく勘を働かせて言い当てたものにすぎないということです。歴史のどの時点においても、その当時に宇宙の仕組みについて「わかっていた」ことの90パーセントは大はずれです。もうひとつ、びっくりすることがあります。私たちが知っていることは、その物事を本当によく観察できる能力の範囲内でしか証明できないということです。言いかえれば、使える道具によって、いつだって制限されるということです。(p.23)
私がよく聞かれるのは、どのようにして折り紙飛行機の世界に足をふみ入れたのか、ということです。しかし実をいうと、私は折り紙飛行機の世界から離れなかっただけです。私は40年以上もの間、紙飛行機を折って飛ばしてきましたが、ある日突然、有名人になったのです。(p.170)
一枚一枚手で折っていく紙飛行機は、大量生産の工業製品とは違って、ひとつとして同じものはない。どんな紙飛行機も、それと全く同じものを再現することはできないし、同じように投げることもできない。1機折るのに30分以上かかり、その機体もせいぜい15回ほど投げると、使えなくなる。うまく折れて、うまく飛んだものも、次の瞬間には激しく墜落して、まがってしまったり、胴体が折れてしまったり、翼が損傷したりしてしまって、別の紙を折る羽目になる。まさにインゴルドがいうように、紙飛行機をつくって飛ばすことは、再び探索すること、そして常に変化する風景としての研究に他ならない。ジョン・コリンズも登山家ではなく、丘歩きの研究者の一人なのだ。

Maker Faire Tokyo 2019で来日したジョン・コリンズさん
科学者は論文を書き、それを学会で発表したり、学術誌に投稿して査読を経て掲載されることで業績とする。それは多くの人がそう信じている、研究者が研究する姿だろう。では、メイカーにとっての研究とはどのようなものだろうか。人類学が「世界中に住まうすべての人の知恵と経験を、どのように生きるのかというこの問いに注ぎ込む」ものだとすれば、「ものをつくることに関するすべての人の知恵と経験を、どのように生きるのかというこの問いに注ぎ込む」のがメイカーである。そんなメイカーの多くは、自分がつくったもので論文を書いたり、その成果を学会に発表しようとはしない。科学者の基準からすれば、メイカーは研究をしていないし、メイカーは研究者ではない。
かつてプログラマーに対して、同じような議論が起こったことがあった。プログラマーは、プログラムを書きたいのであって、(プログラムを書く時間を削って)論文を書きたいわけではない。そうした状況を、普通の(大学教員のような)研究者は嘆くことが多かった。論文を書かないと(研究者の家の中では)評価がされない、研究費が獲得できない、大学のポジションにもつけない……、しかし論文を書かないと良いプログラムが書けない、という声は、ほとんど聞かれなかった。
インゴルドの視点からみれば、紙飛行機を折ることも、プログラムを書くことも、そしてDIYの手作りも、それだけで芸術的な研究、丘歩きとしての研究、好奇心が駆動する研究のひとつである。科学的研究も、デザインにおけるユーザーと同じように、いつのまにか当初のものとは異なった意味や役割が与えられ、競争することの代名詞になってしまった。もちろん、時として競争が必要なことがあるかもしれない。米国のアポロ計画が膨大な予算のもと、驚異的なスピードで進んだのは、東西冷戦を背景にした、米ソの熾烈な宇宙開発競争があったからだ。しかし競争することと研究することには、基本的に何の関係もない。研究は、戦いでもなく、競技でもなく、それは純粋に好奇心に駆動される、ハイキングや散歩のような生きる意志なのだから。
何かを説明しようとすると、すぐに「それ昔やったことあるんですよ」だとか「それって〇〇さんが前にやっていましたよね」という人がいる。自慢したり、知識をひけらかしたいだけかもしれないが、そうでなくても何だかとっても聞き苦しい。人は、だれか他の人がすでに行ったことと同じことをやろうとしても、なかなかそうならない。似たことをしようと思えば思うほど、自分に正直にやろうとすればするほど、決して同じものにはならない。キットづくりが面白いのは、同じキットからさまざまな違うものが生まれてくるからだ。プログラムを書くのが面白いのは、同じアルゴリズムでもさまざまな書き方があるからだ。
山と同じように、ものづくりも常に変化していて、2度と同じ状態になることはない。私たちは、ものをつくっているのではなく、ものづくりに包まれている。だからこそ私たちは、ものをつくることに対する飽くなき欲望(それはおそらく、desire ではなく longing と呼ぶべきものだろう)に駆り立てられて、止むことなくつくり続ける。ものづくりを駆動しているのは、登山家としての成果や達成ではなく、丘歩きとしての好奇心であり、メイカーはものづくりによって世界に参加し、そこで最終的な目的地のないハイキングを楽しみながら、自分の道を見つける。
(続く)
参考文献
[1]野村泰紀(2016)「科学者と哲学者のある交流」Kavli IPMUニュース, No.35, pp.45-57. https://www.ipmu.jp/sites/default/files/imce/press/N35_J04_SpecialContribution.pdf