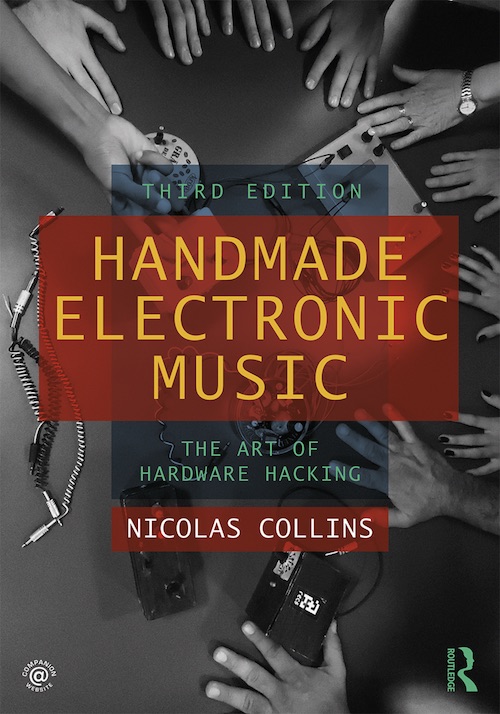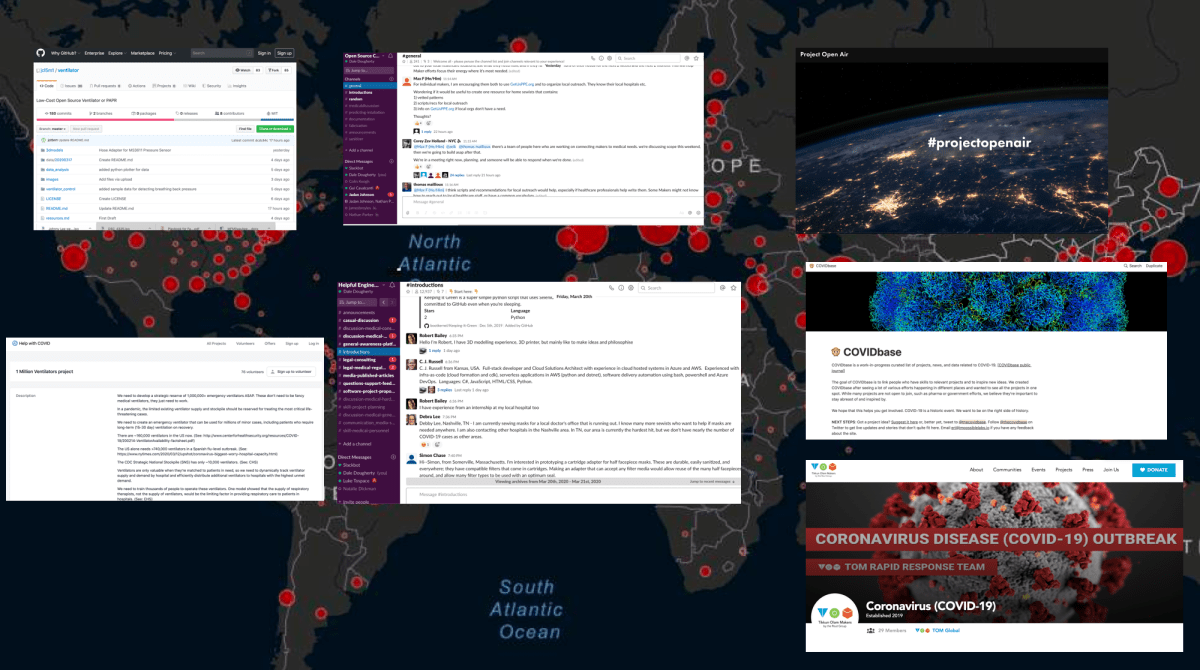本記事は、久保田晃弘さん(多摩美術大学情報デザイン学科 教授)に寄稿していただきました。
1997年に出版された『文化としての20世紀』(東京大学出版会)に「ものにつくられるものづくり」という文章を書いた(『遙かなる他者のためのデザイン』に改訂版を再録)。これは東京大学が行っている公開講座の公講演を1年分まとめて収録したもので、この年のテーマは、もうあと数年で終わろうとしている20世紀の文化を、文学、映画、哲学、科学、教育などのさまざまな視点から考える、というものだった。
このテキストで書きたかったのは、私たち人間がもの(人工物)をつくることは、同時に私たち自身が(自分たちがつくった)ものによってつくられている、ということである。こうした考え方のことを「存在論的デザイン(Ontological Design)」という。この考え方を最初に提示したのは、人工知能の研究者であるテリー・ウィノグラードと、哲学者のフェルナンド・フローレスの共著による『コンピュータと認知を理解する(Understanding Computers and Cognition)」(1987年、日本語版は1989年)である。「新しいデザインの基盤(A New Foundation for Design)」というサブタイトルを持つこの本の序文には、こういう一節がある。
どんな技術でも、人間の本質や活動についての暗黙の理解という「背景」から生まれてくる。一方技術を使うことによって、我々の行動、ひいては存在そのものに根本的な変革がもたらされる。道具(ツール)をデザインするとは自分の存在のあり方をデザインするということだという点に思い至ると、デザインについての根源的な問いに出会うことになる。
存在論的デザインは、まさにこの視点から生まれたものである。そして本の12章「コンピュータを使う—新しいデザインの方向」にはこう書かれている。
デザインで最も重要なのは、存在観を確立するという側面である。ものごとの存在をどう解釈するかという存在観をデザインするというのは、我々が受け継いできた背景とのつながりを保ちながら、すでに(世界的存在として)存在している我々のあり方から芽生えてくるもので、我々がどのような存在であるかに深い影響を及ぼす。
僕が「ものにつくられるものづくり」の冒頭で、茶碗と指の関係を示す写真をあげて考えてもらいたかったのは、まさにこのことだった。

手の動きは(僕が生まれる前から存在している)茶碗によって形づくられている
私たちは、何か人工物というと、それをつくること(人工物のデザインや設計)を考えがちだが、それ以前にまず、私たち自身がすでに存在している人工物によって、いかにつくられているかについて自覚的にならなければならない。人工物によってつくられた存在としての人間というものを想像することなしに、新たな人工物をデザインすることはできない。
最近では、ビアトリス・コロミーナとマーク・ウィグリーによる『我々は 人間 なのか?』(BNN新社,2017年)が、この考え方をさらに今日の電子デバイスにまで展開、拡張している。
人間は、その多様性と可塑性、つまり自身の能力を変化させる能力によって定義される。この可塑性こそが、人間の持つ根源的な不安定性であり、人間が起こす大きな衝撃の基盤になっている。(中略)人間そのものをリ・デザインすることは、地球をリ・デザインすることである。しかし同様かつ同時に、リ・デザインされた世界は、デザインする動物をリ・デザインする。これが、人間であることの真の可塑性である(p.25)。
人間を人間たらしめるものは、体や脳の中でも、また集合的な社会的身体にあるのでもない。それは人工物との相互依存にある。人間は自分たちと人工物との間を、最終的に互いの区別がなくなるほど、複雑に絶え間なく行ったり来たりして漂っている。デザインされた人工物は、一見それを作り出した動物と同じ働きをする。動物が人工物を変形させるのと同じように、人工物も動物を変える。違う言い方をすれば、肉体と脳が人工物になるのだ。(中略)そしてなにより重要なのは、人工物によって与えられた能力を再定義するなかで、人間というものが浮かび上がってくることである。ある意味、人工物は人間よりも人間らしい(p.26)。
ウィノグラードとフローレスの本は出版当時、多くの人に人工知能に対する批判の書といわれた。実際、ウィノグラード自身はそれまで、SHRDLU(シュルドル)というシステムを用いて、仮想的な「積木の世界」の中で、コンピュータが自然言語を理解できるようになることを実証したが、それは同時に、こうした人工的な知能がいかに制限されたもので、脆弱なものかを明るみにした(このシステムについては、深層学習の先駆者であるジェフリー・ヒントンが『人工知能のアーキテクトたち』(オライリー・ジャパン,2020年)のp.108でも言及している)。
しかしこの本の核にあるのは、人工知能というひとつの技術に対する批判というようもむしろ、「合理主義的伝統」という、近代の科学技術全般が「解決すべき問題に直面した時何をするか」ということに対する批判的再検討であった。ここで伝統とは、「可能な答えの空間を規制する了解」のことであり、合理主義的伝統には、以下のような特徴がある。
・状況を、明確に定義された属性をもった、明確な対象によって記述する。
・対象や属性で記述した状況に適用される一般的ルールを見いだす。
・問題となっている状況に、ルールを論理的に適用して、何をすべきかという結論を導く。
ウィノグラードとフローレスの本で、デザインは理解と創造の相互作用(インタラクション)と考えられている。ものづくりにおいても、もののつくりかただけでなく、私たちの理解の中にある暗黙の了解(伝統)を考えること抜きに、ものづくりを考えてもしょうがない。
しかし、先述のヒントンらが切り開いたニューラルネットや深層学習によって、人工知能が再びブームを迎えた今、この本の内容はもはや忘れ去られてしまったように思われる。SNSの普及とそこから生まれたディストピア的な社会状況によって、この合理主義的伝統が、脳としてのコンピュータ、あるいは計算をする機械による知能という私たちの理解や知性に対する認識、そして考えることや知的であることを規定するパラダイムとして、ふたたび社会を広く覆いはじめている。最近はあまり聞かなくなってしまった技術的特異点(シンギュラリティ)も、知性を属性で構成、比較するという合理主義的伝統に沿ったものであるし、脳に電極を埋め込んで操作したり、機械的方法にせよ、生物学的方法にせよ、人間を改造して機能強化することはすべからく、こうした伝統の産物である。前回の「ユーザー」という存在同様に、重要なことは、これらの技術が実現可能かどうかではなく、そうした楽観的技術観がどのようにして今日の人間をかたちづくってきたかである。今日の「人間」や「ユーザー」という存在のありようが、今とは大きく異なる世界も、たくさんあり得るはずなのだ。
その一方で、人類学の分野では「存在論的転回」と呼ばれる大きな動きが起こっている。合理主義的伝統にもとづく、明確な対象としての唯一の<自然>の上で、複数の文化が生み出されているとする「多文化主義」に対置されるかたちで、ヴィヴェイロス・デ・カストロらは、そもそも自然(という身体)が複数存在していると考える「多自然主義」を提唱した。
こうした動きを背景に、文化人類学のフィールドでも、ウィノグラードとフローレスの「存在論的デザイン」が再び注目され始めた。その代表的な事例が、コロンビア出身の人類学者アルトゥロ・エスコバル(Arturo Escobar)が2018年に出版した『Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds(多世界のためのデザイン:ラディカルな相互依存性、自律性、そして世界をつくること)』である。ここで「Pluriverse」とは、「多くの(Pluri-)」という接頭語と、人間の活動の場としての世界を意味する「(Uni)verse」が組み合わさったことばである。

Arturo Escobar『Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds』(Duke Univrsity Press, 2018)
1964年にリリースされたボブ・ディランの名曲「The Times They Are a-Changin’(時代は変る)」の引用から始まるこの本は、
・今日の非持続的社会を作り出した主体はエンジニアリングである
・グランドデザインなき「開発」はデザイン災害である
という認識を出発点に、私たち個人や社会が変化するための具体的/実践的提案を、ラテンアメリカの草の根コミュニティの事例をベースに考察していく。
エスコバルはとりわけ、現代社会の非持続的な危機が、存在や知識、そして実践に対して、私たちの中に深く定着してしまった現在の(既存の)方法の産物であると考えている。したがって、別の(より持続的な)世界をデザインするためには、まず今日のデザインの実践が内包している歴史的、文化的背景を検討し、内省する必要がある。そこで彼はこの、デザインのカルチュラルスタディーズを行うための本を執筆した。
またエスコバルは、今日のデザインに対する批判的問いを考えるための最も適切な方法(アクセスのモード)は、「存在論的(ontological)」なものと考えている。そうした観点から、(このテキストの文脈において)僕がとりわけ重要だと思うのは、第4章の「An Outline of Ontological Design」である。スマートフォンを運ぶメディアとなった私たちは、すでにさまざまなデジタルデバイスによってデザインされている。例えば、エスコバルが本の中で例示しているように、デザイン理論家のベンジャミン・ブラットンが、惑星規模に拡大した計算装置によって「ユーザー/インターフェイス/アドレス/都市/クラウド/地球」という6つのレイヤーからなる「スタック」が出現したというと、本当はそんなものが存在していなくても、多くの人は、あたかもそれがすでにそこにあるかのように考えてしまう。
存在論が重要なのは、それが、ものごとの良し悪しといった価値判断をするためのものではなく、ある問いを立てることが、そもそも必要なのかどうかを考えるためのものであるからだ。
Recasting the question concerning new technologies ontologically is certainly not an issue of total rejection but a redirection of the cultural tradition from which they stemmed.
(新しい技術に関する問いを存在論的に再構築することは、それを拒絶するかどうかではなく、その技術の起源となった文化的伝統を方向転換させるという問題なのです。p.109)
そのためにエスコバルは、ウィノグラードとフローレスの存在論的議論をさらに先に進めていく必要があると主張し、アン=マリー・ウィルスの「We design our world, while our world acts back on us and designs us.(私たちが世界をデザインする一方で、世界は逆に私たちをデザインしています)」[1]というステートメントや、未来に向けて別のアジェンダを提供するための「Defuturing(脱未来化)」に関するトニー・フライのテキスト
We are travelling toward a point at which we will have to learn how to redesign ourselves. This is not as extreme as it sounds, for we have always been a product of design—albeit unknowingly. . . . In essence, what is being suggested here is action towards the relational development of a new kind of ‘human being’.
(私たちは、自分自身をリデザインする方法を学ばなければならない地点に向かって旅をしています。これは、それが聞こえるほど極端なことではありません。私たちは、知らず知らずのうちに、常にデザインの産物であるからです。(中略)要するに、ここで提案されているのは、新しい種類の「人間」の関係性の発展に向けての行動なのです。p.119)
を引用する。「存在論的デザイン」は、人間が何らかの「道具」をデザインすることではなく、人間そのものがデザイン空間の中に存在しているという事実を指し示す。その意味で、存在論的デザインは「人間中心デザイン(Human-centered design)」とは本質的に異なっている。
最後に、この章の締めくくりとしてエスコバルが挙げている、存在論的デザインの特徴を紹介したい。
・すべてのデザインは、私たちがデザインするものによって私たちがデザインされている「世界中世界(world-within-the-world)」を創造している。私たちはすべてデザイナーであり、私たちはみなデザインされている。
・啓蒙(持続不可能、脱未来化、脱世界化、破壊)から持続(未来化、再世界化、創造)への移行のための戦略であり、存在論的な未来化の実践、特に世界と人間の関係的な存在をもたらす実践を含んでいる。
・可能な未来を奪うものづくりを避け、持続不可能性へのテクノロジーの貢献を明らかにする。想像力とテクノロジーを存在論的に結びつけ、技術による人間形成に正面から取り組む。
・ポスト主体であり、ポスト客体である。それは、存在するとみなされている自己(ユーザーや作家)という、技術的合理主義を超えたものである。文明の推移の問題を提起することによって、ポストヒューマンの実践を目指すと共に、人間という支配的なカテゴリーに挑戦する。
・単純なものづくり(ファブ)ではなく、それを明らかにするモードについてのものである。 新しい創作を受け入れながら、単なる技術的なものづくりではない、ものづくりの形を取り戻すことを考える。それは、(西洋の内にあった)デザインの伝統の全体を(それを超えて)非ヨーロッパ中心的に、そして脱植民地的に見ることによって可能になるだろう。
・「選択肢の幅を広げる」(自由主義的自由)のではなく、私たちが望むような存在に変容していくことを意図する。この意味では、潜在的に非資本主義的であり、ポスト資本主義的であり、非自由主義的である。
・生命と地球が内在している自己組織化の能力の上に構築される。人工物の問題に真正面から取り組むが、多様性を構成する生命の複雑なウェブを意識しながら行う。
・生態系の崩壊や不都合な経験を共有することで、人間と非人間の共同体を巻き込んだ共愉的(コンヴィヴィアル)で公共的な道具を奨励する。人間以外から発せられる能動的な力を真摯に受け止めたデザインを心に描き、デザインの場には、常にあらゆる種類の人間と非人間のアクター間の出会いがあることを認識し、生き生きとした物質の肯定的な存在論に基づいて構築する。
・望ましい行為が生成され、解釈される領域をデザインすることで、人間が活動する世界をつくりだす言語の創造に対して明示的に貢献する。行動のための会話の領域をつくりだすことで、それは必然的に(プロトタイピングやシナリオ分析などを経て)デザインから体験へと戻っていく。新しいデザインを創造することが、パワー・ダイナミックス(権力構造)を見過ごすことなく、より良い解釈と行動の領域を出現させることを可能にしているかどうかを問う。
・常に、非人間と、物の実在性と、地球(的なつながり)と、精神と、そしてもちろん(脱植民地的に、排除するのではなく、複数の世界を含むことを考慮して)ラディカルに変容する人間との再接続をもたらす。二元論の解体に貢献し、非二元論的存在のあらゆる形態を真剣に受け止める。最も良い状態になると、それは(より大きな)マインドフルネスへの道を見出し、思いやりとケアの存在論を可能にする。
・すべてのデザインは(ユーザーだけを巻き込むものではなく)能動的に使用するためのものであり、運用上の有効性(ただし、狭義の有用性ではない)を生み出す。生きた実体と異質な生命の集合体(アッサンブラージュ)の自己創出(オートポイエーシス)を育て、多様性の中で生きることを念頭に置く。
「進歩」とは決して正しい答えを見つけようとすることや、ましてやエンパワーメントによって得られるものではない。それはおそらく、有意義な問い、特に新しい存在のあり方を切り開くような問いによって、気づかないうちに少しずつもたらされるものだと(改めて)思う。(続く)
参考文献
[1]Willis, Anne-Marie. “Ontological Designing—Laying the Ground.” Design Philosophy Papers, 2006. https://www.academia.edu/888457/Ontological_designing.