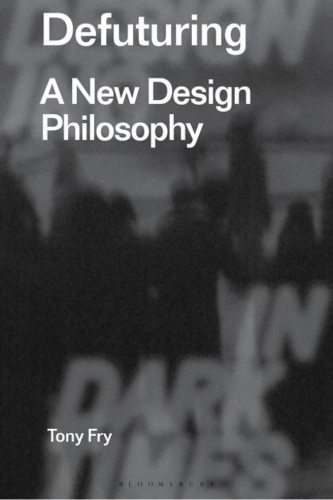本記事は、久保田晃弘さん(多摩美術大学情報デザイン学科 教授)に寄稿していただきました。

『Close to the Edge(危機)』/ Yes
現在の世界の状況は、まさにこのアルバムのタイトル通り縁に近づいている。
(ライブのオフィシャルビデオ:https://youtu.be/BcDU-vilgic)
肯定的デザインの本を開いてみれば、ほぼ間違いなくどの本をみても、その内容は結局のところデザインへの賛辞へと導かれる。ダン&レイビーが『スペキュラティヴ・デザイン』の冒頭で「デザイン特有の楽観主義」と書いたように、伝統的なデザインの世界は、世間のデザインに対する不理解を嘆いたり、誤解を憂うことはあっても、字義通り根拠なき楽天家の集団であるかのような、自己肯定感に満ち溢れている。先が見えないCOVID-19の状況によって、いささかトーンダウンはしたものの、日々紹介される新製品やプレゼンテーション、ワークショップやパフォーマンスの多くは、(いくつかの問題点があげられたとしても)最終的には「あれが良い」だとか「これがすごい」という、(主に当事者自らによる)肯定的言説で締め括られる。それはまるで、デザインとは自画自賛することや、「ほめて育てる」ことのパラフレーズではなないか、と勘違いしてしまうほどである。
もちろん「攻撃は最大の防御」ではないが、「自画自賛は最大の批判封じ」であるし[1]、「ほめて育てる」ことにも、少しはいいところがあるにちがいない。だから、こうした肯定的デザインにも、(少なくともこれまでは)何らかの社会的、経済的、政治的な意味や共同体的な役割があったはずだ。しかし、今日のSNSのような日々の気晴らしや娯楽、あるいはナルシシズムやパワーゲームとしてのデザインから少し目を離してみれば、現代の私たちが直面している環境の問題、経済の問題、文化の問題、そして政治の問題のほとんどが解決不可能であることは明白だ。デザイン思考のワークショップで行われているような、ポストイットを用いたブレインストーミングをしても、ドローイングで視覚化しても、3Dプリンタでプロトタイピングをしても、VRで仮想空間をウォークスルーしても、それら火急の問題が、こうした方法ではもうどうにもならない状況になっていることは、実は多くの人が(口には出さなくとも)気がついている。
いわゆる、デザイン思考的な作業をすべて否定する必要はないし、そこには別の意味や有用さがあるのも確かである。しかしこと「デザイン」や「ものづくり」を批判的に考える時、誰もが口には出さないけれど気がついている問題に対処するにはどうしたらいいか、ということを、やはりどこかで考えていかなければならない。根拠なき楽観主義は、ある種の逃避であり、思考することや批判することをを覆い隠す、反批判主義でもある。少なくとも、現状のさまざまな問題の深刻さを覆い隠したり、そのために現実の世界を指針や規範なく改変することは、事態をより悪化させることが多い。それはおそらく、楽しいものでも、気持ちの良いものでもないだろうし、もちろん肯定的でも、伝統的なものでもない。ダン&レイビーはそのためには「人々の価値観、信念、考え方、行動を変えるしか手はないことは明らかだろう」といった。存在論的デザインの回で述べたように、これらは決して、自然に生まれたものではなく、人々が、特に技術を使う人間が自らつくりだしてきたものである。だとすれば、それらの多くを、つくり直すこともできるはずだ。
こうした肯定的/伝統的デザインの危険性を危惧してきた人たちのひとりに、(アルトゥロ・エスコバルの『Designs for the Pluriverse』でもしばしば引用されていた)デザイン思想家のトニー・フライ(Tony Fry)がいる。フライの名前を多くの人が知ることになったのは、彼が1999年に出版し、昨年「Radical Thinkers in Design」シリーズの一冊としてBloomsburyから復刊された「Defuturing – A New Design Philosophy」である(旧版のプレビュー)。「Futuring」とは、未来について考え、可能性のある結果を想像し、未来を計画するための体系的なプロセスに関する学問である。フライはこの未来学に「De-(~から離れて)」という接頭語をつけて、人間、そして人間が依存している生物圏の未来を否定する行為を「Defuturing(脱あるいは反未来、あるいは離未来というべきか?)」と呼んだ。
Defuturingの背景にあるのは、伝統的デザインというものが、肯定的であるだけでなく、非持続的であることに対する危機感である。これまで何回か述べてきたように、肯定的デザインの一番の、そして本質的な問題点は、それが本質的に大量生産と大量消費という経済原理に根ざしていることだ。肯定的デザインのルーツは工業デザインと広告デザインにある。工業デザインの出発点は、1908年に発表された「T型フォード」である。量産と形式の統一によって価格を抑え、パーツや工程、工具の標準化と分業によって生産性を向上する。こうした効率や最適化という概念に支配されたものづくりは、今日のAppleやTeslaの生産活動にも、脈々と、まさにその肯定的伝統として受け継がれている。こうした反DIY的な、生産=消費概念に根ざした近代デザインの思想が、資本主義や商業主義の手段となり、さらに今日の新自由経済とものづくりが深く結びついている限り、それは決して「持続可能」なものにはならない。
そんな持続不可能なデザイン(を語ったり実践している人)が、大好きなキーワードは「未来」である。持続不可能なものづくりを行っている人や企業ほど、何故か未来を語りたがる。コンピュータの未来、自動車の未来、社会の未来、世界の未来…… 人工知能も、シンギュラリティーも、ポストヒューマンも、デザイナーが語るとすべて未来の話につながっていく。しかしながら、こうした未来はすべからく、現在の延長線上にしかない。本当の未来ではなく、自分たちが今行っていることを変えなくても良い、あるいはより推進する、現在の延長としての偽りの未来である。現在の非持続的なものづくりを行い続ければ、そんなすばらしい偽りの未来がつくられるはずはなく、単に未来が消滅するだけである(例えば、ジェームズ・ブライドル著『ニュー・ダーク・エイジ』の第三章「気候」を参照のこと)。フライは、こうした「未来の消滅」に対して、理性と思想を持って、きちんと対峙すべきだと主張する。
『Defuturing』の2020年度版の序文にはこういう一節がある。
Even so there are many people living with the misplaced belief that no matter the problem, technology will be the salvation force.
(たとえどんな問題が起こっても、技術が救いの力になるという、見当違いの信念を持って生きている人がたくさんいる)In truth, the greater our species instrumental attainments, the more anthropocentrism and technocentrism converge.
(実際、私たちの種の道具/装置的な達成度が高くなればなるほど、人間中心主義と技術中心主義に収斂していく)
フライがこの20年以上に渡って語り続けているDefuturingとは、私たちの現代的な、非持続的生活様式によって、人間の未来が損なわれてしまう状況のことである。今日の人間社会の行動、欲望、社会関係、技術、制度、物質的・文化的な生産システムのダイナミズムによって駆動させられた生活は、このDefuturingの条件をきちんと満たしている。未来を消滅する、非持続的な「ものにつくられるものづくり」を続けてきたため、私たちの「存在している」「生きている」という感覚も、肯定的デザインによって形作られている。フライはこうしたDefuturingというデッドエンドから逃れるために、デザイナーが自らの実践を批判し、改革することを求める。さらに、それを最も妨げているのが、現在のデザイン教育であると強く主張する。

(映像リンク:https://youtu.be/mpFhpuK3vIc)
フライ自身によるDefuturingの紹介ビデオ。デザインを未来化するためには、新たなデザイン哲学が必要である。このビデオも、デザイン教育の重要性と、その変革の必要性を主張して終わる。
美術大学で仕事をしている僕自身も当事者の一人である、この「デザイン教育」の問題を批判的に考察するために、フライが17年に「Design Philosophy Papers (DPP)」で発表した『Design after design(デザイン後のデザイン)』という論文を紹介したい。DPPは、フライのパートナーのアン=マリー・ウィリスが、2003年に立ち上げたデザイン哲学論文誌であり、この「Design after design」はその最終号に掲載されている。実際このわずか4ページの論文は、フライがDPPを中心として、持続的なデザイン哲学について書いてきた多くのことがらを、選択的に再検討し、改訂、加筆した総括的なものとなっている。
この論文は、現状の肯定的/伝統的デザインに対する認識と批判から始まる。
・デザインは、その経済的な機能にかかわらず、全体としてはただの肯定的な変化の手段となり、今日ほどその重要性が低くなったことはない。
・デザイン業界は、自由奔放な消費者主義の市場に迎合し、エレガントで持続不可能なオブジェクトを再統合し、スタイル第一の製品に賞を与え、フォトジェニックな建物を設計し続けている。
・デザイン研究の学会は、研究者を内向きにさせ、政治的なものとは向き合わずに、研究者同士の内輪で話し合うだけで、過去の論文を再生産し続けている。
・境界を越えて、ポスト道具主義を実践する進歩的なデザイナーが存在してはいるが、彼/彼女らは散らばっていて、数も少ない。
こうした現状を踏まえてフライは、私たちは持続不可能性を構築している膨大な数のデザインを、人類学におけるエージェンシーの観点から理解しなければならないという。そうすることで始めて、現在「持続可能な解決策」とされている、実際には正しくない実践を、批判的に見ることができるようになる。今日、デザインの重要性は限りなく低くなってしまったが、だからこそデザインを、少しでも重要なものにしなければならない。しかし問題は、誰がどのようにして、それを行うのか、ということである。この問いに対する答えがあるとすれば、それは一人の人間から得られたり、あるいは多大な時間と労力をかけずに、即座に得られるものではない。
まず認識しなければならないのは、
・理想主義的な答えは答えにならない
・実践的/道具的な答えは答えにならない
・答えが何であれ、それは試された要素の蓄積になる
ことである。その上で、私たちの種が未来に到達するためには、
・解決できる問題
・適応できる問題
・私たちが対処することができない問題
のそれぞれがあることを適切に区別して、相互に結びついた巨大な課題の集合体に取り組むために、今までにない想像力の山を登っていく必要がある。
フライは、フランスの社会学者ブルデューの「ハビトゥス(人々の日常経験において蓄積されていくが、個人にそれと自覚されない知覚・思考・行為を生み出す性向)」を引き合いに出しながら、エスコバルと同じく、存在論的デザイン—デザインされる必要があるものをデザインし直すために、自分自身をデザインする必要があること—を主張する。デザインを自分自身のものにするということは「内在的」な視点を持つ、ということでもある。
フライは、現状のデザイナーの典型を以下の4つに分類する(面白い!)。
・主流派:主流になることに夢中になっている建築家やデザイナー。制約のない野心、デザインしたモノに対するフェティシズム、市場での成功、無批判な文化的認知。ある者は成功した皮肉屋になり、ある者は皮肉な失敗者になる。
・政治的ロマン主義者:主流派に似ているが、自分自身、デザイン、デザインされたもの、そして違いを生み出す能力に対する自分自身の空想を信じ、妄想の世界を創造するナルシシスト。
・リベラルな改革派:市場のデザインに批判的であるが、改革主義が本当の変化をもたらすと信じている。その先端的な「持続可能性」は、ほとんど全くと言っていいほど、持続不可能なものの規模と深さに立ち向かうことができない。その結果、持続可能性の名の下に、多くの持続不可能なものが持続されている。結局、リベラルな改革派は、弱体化した政治的ロマン主義者にすぎない。
・内部的アウトサイダー:覇権的な技術資本主義に外側はない。内部的アウトサイダーは、孤立と創造的な論争に自らを位置付ける。ノスタルジアを持たず、過去を資源として捉え、経済的利己心を超えて行動し、程度の差こそあれリスクを受け入れる。その気質は肯定的、野心、反キャリア、新しい学び、そして有効性にある。
あたりまえのことであるが、持続的でないデザインは持続しない。フライは、そうした非持続的なデザインがまずイノベーションすべき対象は、デザイン自体であると考え、特にその変革の鍵が「デザイン教育」にあるとする。ここでもやはり、デザイン教育の批判的な現状認識から始まる。
・現在のデザイン教育は、「ハウツー」という道具主義に支配された、劣化した教育形態であり、卒業生を労働市場に誘導するための、静かな被災地である。
・そこを支配しているのは、以下の2つの指標である。
-(教育機関の収入をあげるためにレベルを下げた)志願者数
-(業界のニーズに応えるための道具主義とサービスを推進する)卒業生の就職
・知的で洞察力に富み、世間体を気にしない教育者は少数であり、多くの時間労働者は、業務をただ遂行するだけで、コンプライアンス(法令遵守)の文化を形成している。より大きな将来のニーズのほとんどが見落とされている。
こうしたデザイン教育という災害に対処するためには、以下のような、別の方向性が必要であることをフライは提案する。
・Re(at)traction(撤回と再吸引):まず最初に行うべきは、教育機関の規模を小さくすることである。学生数は少ないが、より多様性のある地域からの入学者を増やし、選抜の基準も高くする。その後の学生の成長は、スタッフとそこで実行される教育の質による。
・新しいカリキュラム:
- 社会・政治的に関与する(オブジェクトよりも)プロセスとしての(しかしデザインプロセスではない)プロセスに基づいたもの。
-(新しいものよりも)リメイクに基づいたもの。
このようなカリキュラムは、年単位のものではなく連続的なものであり、そこには、以下のような内容のものが含まれる。
・レトロフィットとメトロフィット:「ありのまま」を志向することと、リダイレクト的な(既存のデザイン分野を分解し、他の分野に開放することで、多様な学習と探求のチームを生み出す)デザインの実践。
・状況的な問題研究の場:問題と共に生活し、作業や制作することに基づいた内在的なもの。
・異文化リテラシーとデザインの哲学:異なる宇宙観、存在様式、種の未来を理解するためのもの。
・デザインのアクター・リーダー:サービスの提供者ではなく、プロジェクトの創造を通じたリーダーシップ。どのようにカウンターデザインの経済を確立するかに焦点を当てる。
重要なのは、従来の「寺子屋」のような手習いの文化ではなく、プロジェクトが全体の中心になることである。他には「時間の中のデザイン(未来からの設計)」、「脱植民地主義(植民地主義のグローバルな影の中でのデザイン)」、「デザインフィクションの力(デザイン行為のオーサリング)」、「デザインと危機の状況(例えば「心と身体の不安」のような)」、「公共的にデザインされた変化(例えば「刑務所」のような)」、そして「種の変容(人間のunmaking/remakings)」のようなテーマが考えられる。さらに以下のような項目が必要となるだろう。
・カウンターコースのための場と支援:学生は、肯定的な状況から変化していくエートス(精神)によって、独自の学習イベントを制作するよう促される。さらに、ある特定のプロジェクトの現実的な問題に対応するために、そこで「知っておくべきことがら」に関するワークショップを提供する。
・世界像の内の生活:社会的学習は、デザイン教育の後のデザインの新しいパラダイムの一部でなければならない。例えば(学生から提案されるか、またはニュースから)「今日のテーマ」から始まるものや、定期的に行われる読書グループ(例えば金曜日の午後だとか)。月に一度のホットな話題のワークショップでは、経験から得た問題や問題を取り上げていく。
・ワークネットの形成:「チームでの働き方を学ぶ」だけではなく、卒業後の経済的、文化的、政治的な生活にまで拡がる可能性を秘めた「(組織化された個人、集団的な作業として)チームで学び、チームで働くこと」に基づいた教育履歴を確立する。批判的なデザインを学んだ学生にとって、現在の仕事は魅力的ではない。バンドが結成され、メンバーが変わることもあれば、何十年も続くこともあり、人々はバンドの間を移動していく。バンド/アンサンブルのジャンルやアイデンティティーは多岐にわたる。まさに「Band on the Run」である。
フライが示すような、デザイン教育の変革を実現するためには、まず、現在の大学や教育機関における、カリキュラムの内容や教員、スタッフを大量に入れ替える必要がある。まずは、それを実現するためのプロセスをデザインすることが、大きな課題となる。新しいプログラムを提供し、実践する人自体が変化しない限り、何も変わらないだろう。新しい種類の専門家が必要とされている。
フライは現在、オーストラリアの州のひとつであるタスマニアに「
The Studio at the Edge of the World(世界の縁にあるスタジオ)」を設立し、そこを拠点として精力的に活動を続けている。南極大陸に最も近い陸地でもある島州のタスマニアは、世界的な海面上昇の震源地でもある。フライはそこで私たち人類が、環境、社会、地政学、経済の持続不可能性が融合した、まさに災害の縁(Close to the Edge)に瀕している現実と、日々向かい合いながらデザインについて考えている。
フライのテキストを読みながら、未来について考えている時にふと思い出されたのが、1967年にクリス・マルケルが制作したオムニバス・ドキュメンタリー映画『ベトナムから遠く離れて』である。この映画にはマルケル以外に、ヨリス・イヴェンス(オランダ)、アラン・レネ、アニエス・ヴァルダ、クロード・ルルーシュ、ジャン=リュック・ゴダール(以上フランス)、ウィリアム・クライン(アメリカ)という六人の映画監督が参加した。富める強者アメリカと貧しい弱者ベトナムの対比(ハノイ空爆のニュースフィルム)から始まり、最後の1967年4月のニューヨークでの大規模な反戦運動まで、タイトル通り当時大きな社会問題となっていたベトナム戦争に関する、優れた批判的ドキュメンタリーである。
イントロダクションとエンディングを含めて、全体は13の部分に分かれているが、第六章のジャン=リュック・ゴダール監督による『カメラ・アイ』の独白には特に考えさせられる。そこで、この部分の「ベトナム」を「未来」に入れ替えてみた(一部抜粋)。
我々は未来から遠く離れたところにいる
心を痛めていると皆言う
確かにその通りだ
心を痛めている
だが我々は実際に血を流しているか?
つまりそのことが問題なのだ
うしろめたさを感じてしまう
何か恥ずかしい気になる
平和を訴える署名をする時に感じるような
そこで考えた
我々にできるただ一つのことは
未来にむりやり入り込む事ではなく
何が何でもムリに入り込むんではなくて
反対に未来が
我々の方に入り込むにまかせる
日常の我々の生活の中に
そうすれば
わかってくるんだ
つまり未来は
未来だけの問題ではないことが
「未来を作れ」という事は
自分の中に未来を作る事だ
未来はおそらく、予測したり発明したりするようなものではない。むしろ、未来の方が自分の中に入り込んでくるようにしたい。未来をつくるのではなく、やってくるようにする。それこそが、持続的であるということであり、肯定的デザインによって消滅した未来を、再び出現させることではないだろうか。
現在の延長線上でない未来を迎え入れるためには、不連続な未来を想像できなければならない。それは、スペキュラティヴ・デザインのように、未来を道具として用いることとも違う。不連続な未来を想像すること—それは一般的な手順では導くことができない特異点であり、私たちが考えるべきデザイン・シンギュラリティでもある(技術を再帰的、漸次的にバージョンアップすることで生じる技術的特異点は、本当の意味での特異点とはいえない)。そしてその特異点から逆算された現在、すなわち「Reverse Futuring」によって、現在の行動指針が生まれる。未来を出現させるためには、時間を逆行させることが必要だ。
理論物理学者のアルベルト・アインシュタインはこんなことを言っている。
“We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”
(問題をつくり出した時と同じような考え方では、問題は解決できない)
世界の非持続性をつくり出した肯定的デザインの思考では、非持続性の問題を解決することはできない。離れていくばかりの未来を、もう一度私たちの手元に引き寄せるためには、別の異なる考え方が必要とされる。
(つづく)
[1]バイロン・リーブス,クリフォード・ナス『人はなぜコンピューターを人間として扱うか ―「メディアの等式」の心理学』 細馬宏通訳,翔泳社(2001)