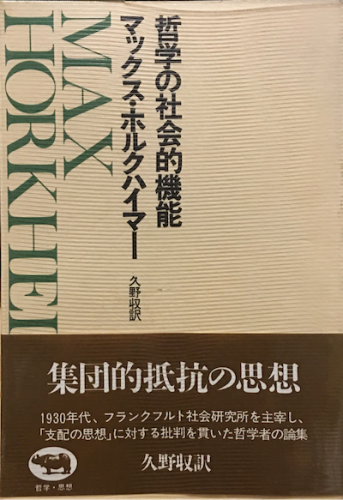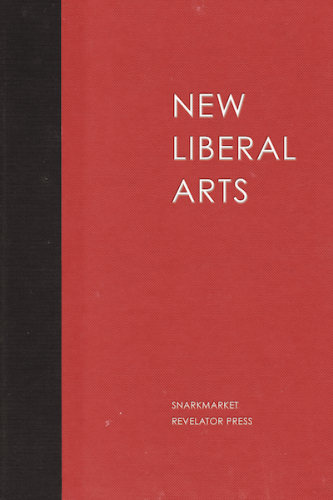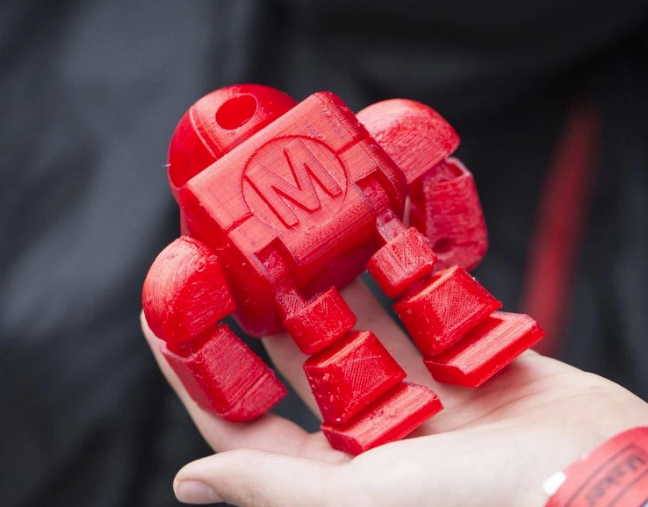本記事は、久保田晃弘さん(多摩美術大学情報デザイン学科 教授)に寄稿していただきました。

左から二人目がマックス・ホルクハイマー、その右がテオドール・アドルノ、一番右がユルゲン・ハーバーマス。写真はWikimedia Commonsからの転載(CC BY-SA 3.0)。
前回のクリティカル・メイキング、そしてクリティカル・デザインやクリティカル・シンキングなど、最近「クリティカル」という言葉を見ることが多くなってきた。クリティカルとは、字義どおりには「批判的」「批評的」あるいは「危機的な」「重要な」という意味を持つ、ややネガティヴな印象を与えかねない単語である。しかし、この言葉を単なる日常的な感覚での「批判」や「批評」と捉えただけでは、その意味を考えるには、少々不十分であるように思う。なぜなら「クリティカル」という概念には、20世紀の社会哲学史における、複雑な経緯と重要な役割があるからだ。
マックス・ホルクハイマーという1895年生まれのドイツの社会哲学者は、1937年に「伝統的理論と批判的理論」という論文を発表した[1]。この論文には、ホルクハイマーが二代目の所長を務め、後にアドルノやベンヤミンも参加した「フランクフルト社会研究所(フランクフルト学派)」の思想的代名詞となった、「批判理論(クリティカル・セオリー)」の基本的な考え方が述べられている。
ホルクハイマーの批判理論とは、何かしらの教義を主張するための学説としてではなく、ものごとについて深く考え、社会をより良くしようとするための方法論として提起された。そしてそれは、アメリカの哲学者チャールズ・サンダース・パースが19世紀に提唱した、プラグマティズムにおける「間違い主義」、すなわち「人間のあらゆる知識、原理的に常に間違い得る」「人間は間違いを犯し、それを修正することによってのみ真理に到達できる」という主張のように[2]、今なお、ある種の普遍性と有効性を持った方法論のひとつである。
批判理論が問題にしたのは、論文のタイトルにあるように、デカルト以降主流となった、伝統的な理論の組み立て方(伝統理論)であった。ここで伝統理論とは、
・命題を矛盾なく整合的に示す
・主観と客観を分離する(客観は主観に影響されない)
・定量化や統計、再現性に基礎付けられる
・自身を社会の中に位置付けることができない
といった特徴をもつ理論のことで、今日の専門領域に分けられた学問のほとんどが、この自然科学的方法を抽象した伝統理論に基づいている。伝統理論はボトムアップであるが故、それぞれの分野における発見や発明は、基本的にその分野の中(例えば学会や論文誌)だけで議論、評価され、「そもそもこの学問に意味はあるのか」「本当にこの学問は必要か」といった根本的な問いかけは、エラーあるいは例外となり、タブー視される。いいかえれば、伝統理論とは社会や学問の現状を受け入れ、それを肯定することを前提とした、既存の学問のための理論であるといえるだろう。
それに対して、ホルクハイマーが提唱した批判理論は、こうした伝統理論やそこで前提とされている、ものごとの考え方自体を疑うことから出発するもので、以下のような特徴を持つ。
・社会自体が矛盾に満ちていることを踏まえて、理論の中にも矛盾を許容する
・理論とは社会の自己意識であり、主観と客観に分けることはできない
・個別の学問の成果を、実践を通じて集約していく
・現状維持ではなく、社会をより良く変革することを目的とする
伝統理論が、自然にせよ、人間にせよ、設定された客観的対象を矛盾なく記述するための言語で書かれているとすれば、批判理論は自らを変えていくための、遂行的(パフォーマティヴ)な言語で書かれている。だからこそ、例外処理としての批判理論は、パースの間違い主義のように、矛盾に満ちたこの現実世界を、少しずつ変えていくことができる(はずだ)。
この伝統理論と批判理論の対比は、クリティカル・デザインやスペキュラティヴ・デザインの、理論的な基盤にもなっている。例えば、スペキュラティヴ・デザインの中でダン&レイビーが示したA/Bデザインの対比は、この伝統理論と批判理論の対比に対応している。伝統的デザインとは、資本主義や商業主義のような現状を肯定する記述的デザインであり、批判的デザインとは、解決する方法が見つからない、さまざまな矛盾を抱えた現状を、少しずつ変革するための遂行的デザインである。
GAFAのようなビックテックや、現状のデザイン業界や学会を所与のものとして受け入れる伝統的デザインには「デザインが現実世界の中で、どのような意味を持ち得るのか」を議論したり、社会全体の中にデザインを位置付けることはできない。伝統的デザインは、大企業にとっての子会社のように、現行の社会の中の個別領域(下位概念)であり、そこで行われる活動も、ある個別領域内での意味や価値観に基づいた発明、あるいは技術開発のひとつにしか過ぎない。
肯定的であるということは、断定的であるということでもある。例えば、伝統的デザインにおいて、使いやすさは肯定的である。使いやすいデザインと使いにくいデザインがあることが、事前に定められ、「使いにくさの中に使いやすさがある」あるいは「使いやすさの中に使いにくさがある」というような、使いやすさ(良いデザイン)と使いにくさ(悪いデザイン)の間の矛盾は許されない。
批判理論における批判とは、社会の中に潜む隠れた矛盾を顕在化させることである。今日の社会だけでなく、デザインやものづくりにも、矛盾が満ち溢れている。例えば、ものをつくり、それを日々消費、廃棄しながらも、環境に配慮しているといわなくてはならない矛盾。そこには、広告による欲望の人為的拡大や、本当は長く使えるものがありながら、周期的に発表される新商品を購入させようとするマーケティングに対する現状肯定がある。ひとりひとりの個人は主体的に行動しているように見えるにもかかわらず、社会全体は宿命的かつ超越的で、個人の力など取るに足らないように感じさせる見えない力。その力のもとでは、個人という主観と社会という客観が分離され、主観(個人)によって客観(社会)は変化しないという、自然諸科学的な伝統的価値観が、暗黙の内に蔓延する。
商品や市場といった今日の前提(現状)を疑うことから出発する批判的デザインは、伝統的デザインにおける主体と客体の分離、個人と社会の分離こそを矛盾として捉える。そしてホルクハイマーが、感性と理性を結びつける構想力を「社会」と呼んだように、矛盾に満ちたこの社会において、感性と悟性(理解)を結びつけようとするのが、批判的デザインである。今日の新自由主義社会における自己責任、あるいは伝統理論における人間中心主義など、すべては矛盾のかたまりである。批判的デザインとは、そうした矛盾を孕みながらも、それに対して目をつぶることも、諦めることもせず、少しずつ良く生き続けていくための実践を引き出す、遂行的な理論のひとつなのである。
批判的デザインの一例:地球温暖化に対する問題提起のために、フィンランドで最も寒い北極圏の村「サッラ」が制作した、2032年オリンピック開催地立候補ビデオ。逆説的なメッセージだけでなく、暑さで溶ける氷山のロゴや、熱中症のトナカイのマスコットなど、さまざまなプロップが制作されている。https://www.savesalla.com/
しかしながら、のちに哲学者のユルゲン・ハーバーマスが指摘したように、批判理論には大きな問題点もある。その一つは、批判理論において、批判(相対化)の基準する現状や現実社会をどのように捉えるか、さらにそれらを批判によって変革していく際の目標をどこに置くか、ということである。現状の矛盾を指摘することはたやすい。しかし、批判された社会の何をどのように、どちらに向かって変革していけばいいのか。そうした批判理論における出発点と目標は、批判理論それ自体の中には書かれていない。
とはいえ、批判理論といえども、それが何らかの明確な目標を事前に持っていたとしたら、そして批判による変革の方向性を、常にあるひとつの目標に向け続けていたとしたら、それは批判ではなく、単なるドグマに堕ちてしまう。プラグマティズムの「間違い主義」がそうであるように、真理(と呼び得るもの)は常に私たちの経験的知識の達し得ない所にある。批判理論が、既存のあらゆる枠組みを(所与のものとせず)疑うことから出発するとすれば、自明な目標だけでなく、個人の専門や既存の分野なども、常に批判の対象となる。重要なことは、(批判)理論は決して実践に飲み込まれてはならない、ということだ。理論は理論として、常に自立して批判の主体であり、批判の客体でもなければならない、それこそが、学問の自由ということでもある。
自明の目標やドグマを持ち得ないとすれば、批判理論の「規範的基礎」なるものを、一体どこから導き、どこにおけばいいのだろうか。
前回の連載の最後に、批判的理論を個人的なレベルの日常生活に関連付けることの難しさの要因が、制度化されたアカデミズム内の「関心」ごとの違いにあると書いた。伝統理論とは、まさにこの制度化されたアカデミズムにおける理論に他ならない。効率良く成果(論文)を生産するためには、研究室の目標を客観的に定義し、そこで研究する(働く)研究者や学生は、その前提や目標を疑うことなく、分業化された工場のような方法で、効率良く学問研究に取り組む。その結果、論文の生産性や効率を高めることができる。それこそが伝統理論の、最も役に立つ使用法である。しかし、批判理論の視点からは、学問や研究を、工場や工業のメタファーで語ることはできない。
批判とは、答えのない問いを考え続けることである。同様に、批判的ものづくり(クリティカル・メイキング)とは、何かをつくることを「答え」や「成果」にしないことである。批判とは、自分が今、基礎としているものを、常に疑い続けることである。学際的、領域横断的であるということは、他の領域の知見を、自分の領域の中に取り込む、つまり自分の規範の中に押し込めようとすることではない。学際的であるためには、自分を含め周囲の人たちが、暗黙のうちに自明としていることを疑い、多くの場合そこに潜んでいる矛盾を批判的に明るみにすることである。学際的であるということは、自分の基盤を変化させるということであり、そのためには、まず批判的でなければならない。自分の分野や領域に対して肯定的である人は、決して学際的になることはできない。何かをつくることも同様である。ものをつくることを、無批判に楽しんだり、肯定するだけの伝統的ものづくりは、自分が閉じ込められている世界の内でのパワーゲームに陥ることはあったとしても、けっしてそこから飛び出して、より広い社会の中にものづくりを新しく位置付け直すことはできない。
今日のものづくりは、それ自身の中にさまざまな矛盾を抱えている。資源や環境の有限性、あるいは地球温暖化のような全地球的な問題が顕在化した人新世の時代には、そうした矛盾がいたるところに噴出している。ものづくりを、単なる楽しさや経済的目的、あるいは有用性で語ることはできない。だからこそ、批判的ものづくりが必要なのだ。
では、批判的にものごとを考えていくためには、具体的にどうすればいいのだろうか。僕は、その一つの方法が、新しい「リベラル・アーツ」を議論することだと考えている。古代ギリシア、ローマで生まれたリベラル・アーツの概念は、その後言語系の3学(文法・修辞・論理)と、数学系の4科(算術・幾何・天文・音楽)で構成される自由七科として構成されるようになった。ここで「自由」ということばが用いられているのは、リベラル・アーツというものが、人々を束縛から解放する、自由のための諸技術であると考えられていたからだ。リベラル・アーツは、人々のものの見方や考え方を束縛している前提を疑い、そこから解放されること、つまり批判理論を実践に結びつける。
しかし、このリベラル・アーツといえども、それだけでは既存のリベラル・アーツ、すなわち自由七科自体を疑うことから逃れ得ない。リベラル・アーツ自体も、間違い主義によって常に、その間違いを修正し、リベラル・アーツの外へと変化していくことが必要不可欠である。
そうした姿勢を実践した一つの例が、2009年に行われた「ニュー・リベラル・アーツ」というプロジェクトである。その序文の抄訳をまずは紹介したい。
この本はブログから始まった。21世紀的な言い方をすれば、それは会話から始まったということになる。
この会話はブロガーのJason Kottkeから始まった。彼はまず「リベラルアーツ2.0」という言葉を造り出し、Timothy CarmodyとRobin Sloan、そして共同ブロガーのMatt ThompsonがSnarkmarketのコミュニティーに投稿を続けると、そこにスレッドが形成され始めた。
つまりこれは大まかに言うと、21世紀のリベラルアーツの方法を、共同的に探求するためのアイデアである。
しかし、21世紀の賢人のためのリベラルアーツとは、望遠鏡を持った天文学者、つまり適切な道具を手に入れた人にとっては、古代の神話のようなものかもしれない。もしそうだとすれば、新しいリベラルアーツはおろか、そもそもリベラルアーツのようなものが不要になってしまう。必要なのは、新しい科学技術と、その使い方だけになる。
あるいは、新しい科学技術で解決できない問題は、人間の本性の最も深い部分にある、不変の矛盾だけかもしれない。もしそうだとすれば、私たちはリベラルアーツを更新する必要はない。
つまり「リベラルアーツ」という名前は、多くの人にとって、古代のものと同じくらい永続性のある学問を連想させる。
古代ローマでは、医学や建築などの学問は、実用的すぎるという理由で、当時のリベラルアーツ(自由七科)から除外されていた。ルネサンスの時代に、アルスとテクネの境界線に悩まされたのは絵画と彫刻だったが、自由人の教育に最も適した学問であるリベラルアーツの基本的な考え方は、一向に変わらなかった。
しかし、19世紀になると、特にアメリカでは近代大学の創設に伴い、リベラルアーツは大きく変化した。化学、解剖学、物理学などの精密科学(exact sciences)が、高等専門学校からリベラルな大学へと移行していった。
こうして、ハーバードやマサチューセッツ工科大学(MIT)のような学校が、互いにアイデアやリソースを共有し、後に学生や教授を奪い合うようになっていった。
つまり、リベラルアーツも、私たちと同じように常に変化してきた。
新しい世紀を迎えた今こそは、このリベラル・アーツの変化に注力するのに適した時期だといえる。すでに何が変わったのかを見直し、今、何が変化しつつあるのかを明確にし、さらにそれらの変化を推し進めるために。
そこで新しいリベラルアーツを紹介したい。
しかし、ここで定型的なリベラル・アーツのリストを作りたいわけではない。むしろ、いろいろなことを書き並べた長々としたリスト(laundry list)を作りたいと考えている。私たちは賢く、挑発的で、洞察力があり、意外性があり、かつ/あるいは笑えるような、新しいリベラルアーツの売り口上を求めている。
だからこれは、定義ではなく、ユニークな新しい学校、つまりリベラルアーツ・カレッジ2.0のコースカタログを、垣間見るためのものである。
他のカタログと同じように、これは前から順に後ろまできちんと読むような本ではない。項目はアルファベット順に掲載されていて、ランダムにアクセスできるようになっている。まずは興味がありそうなページをめくって、感想述べたり、会話に参加して欲しい。
ウェブ上で読んだり、PDFファイルをダウンロードできる、この本の中に挙げられた、さまざまな文体が入り混じったランドリー・リスト(新しいリベラルアーツのための雑多な売り口上)は、以下の通りである。
・Attention Economics(注目経済学)
・Brevity(簡潔さ)
・Coding And Decoding(コーディングとデコーディング)
・Creativity(創造性)
・Finding(発見)
・Food(食物)
・Genderfuck(ジェンダーファック)
・Home Economics(家政学)
・Inaccuracy(不正確さ)
・Iteration(繰り返し)
・Journalism(ジャーナリズム)
・Mapping(マッピング)
・Marketing(マーケティング)
・Micropolitics(ミクロ政治学)
・Myth And Magic(神話と魔法)
・Negotiation(交渉)
・Photography(写真)
・Play(遊び)
・Reality Engineering(リアリティー工学)
・Translation(翻訳)
・Video Literacy(映像リテラシー)
この本が公開されてから、すでに10年以上たっているが、ここで挙げられたリストは、今なお批判的に考え続けたくなる項目ばかりである。トランプ前米大統領も多用した、twitterの簡潔なメッセージは、バズることを目的とした典型的な注目経済の源泉であるし、それが今日のマーケティング=情報のパンデミックの、ひとつの要因ともなっている。コーディングとデコーディングは、プログラミングに限らず、コミュニケーションのすべてのモードにかかわり、身体技法としての創造性と(スマートフォンでGoogleにアクセスするような)検索としての発見は、表裏一体の関係にある。食物や家政学は、今日議論すべき最も重要なテーマのひとつである、気候変動や持続可能性と深く結びついている。ジェンダーファック(性別なんてクソ食らえ!)は、今日のLGBTの問題そのものであり、おそらく今であれば、BLM運動もリベラルアーツで取り上げるべきテーマのひとつになるだろう。
人々がグローバルに移動できなくなってしまったCOVID-19の状況下では、日常の自治、地域コミュニティーに限らず、あらゆる政治がミクロになり、コミュニティーとの会話として再定義されるジャーナリズムや、異分野理解としての翻訳の役割も、大きく変わりつつある。なぜなら、「自分は正しい」と思っている人に対する嫌悪感から生まれるフェイクニュースや陰謀論は、いわば意図的に不正確にすることの技芸であり、神話という物語の力や、魔法という神話を生み出す力と深く関わっているからだ。
始まりも終わりもない、解放としての反復=間違い主義を実践するには、相手を対等な存在として認め、自己の否定をも厭わない交渉と協力が必要であり、そうすることで始めて、自分というつくられた存在を超えていくことができる。総合科学、そして比較文学でもある写真によって、知識と技術の間の境界線が曖昧になり、さらにリアリティー工学や遊び(ゲーム)によって生成された現実=映像のオンラインプラットフォームによるインフレーションが、映像リテラシーの必要性を、改めて強調する。
こうした新しいリベラルアーツは、Gitのような分散リポジトリで議論され続けるのが相応しい、オープンエンドで常に変化し続ける、ダイナミックな批判的学問である。私たちは、このランドリー・リストを、さらに長くしていかなければならない。
(続く)
[1]マックス・ホルクハイマー『哲学の社会的機能』久野収訳,晶文社(1974)
[2]鶴見俊輔『アメリカ哲学』講談社学術文庫(1986)