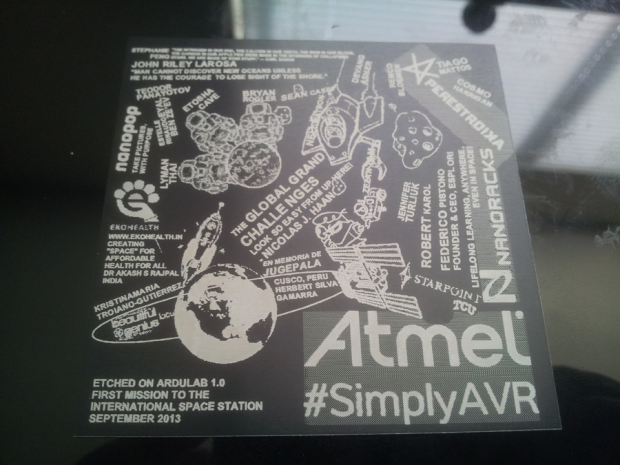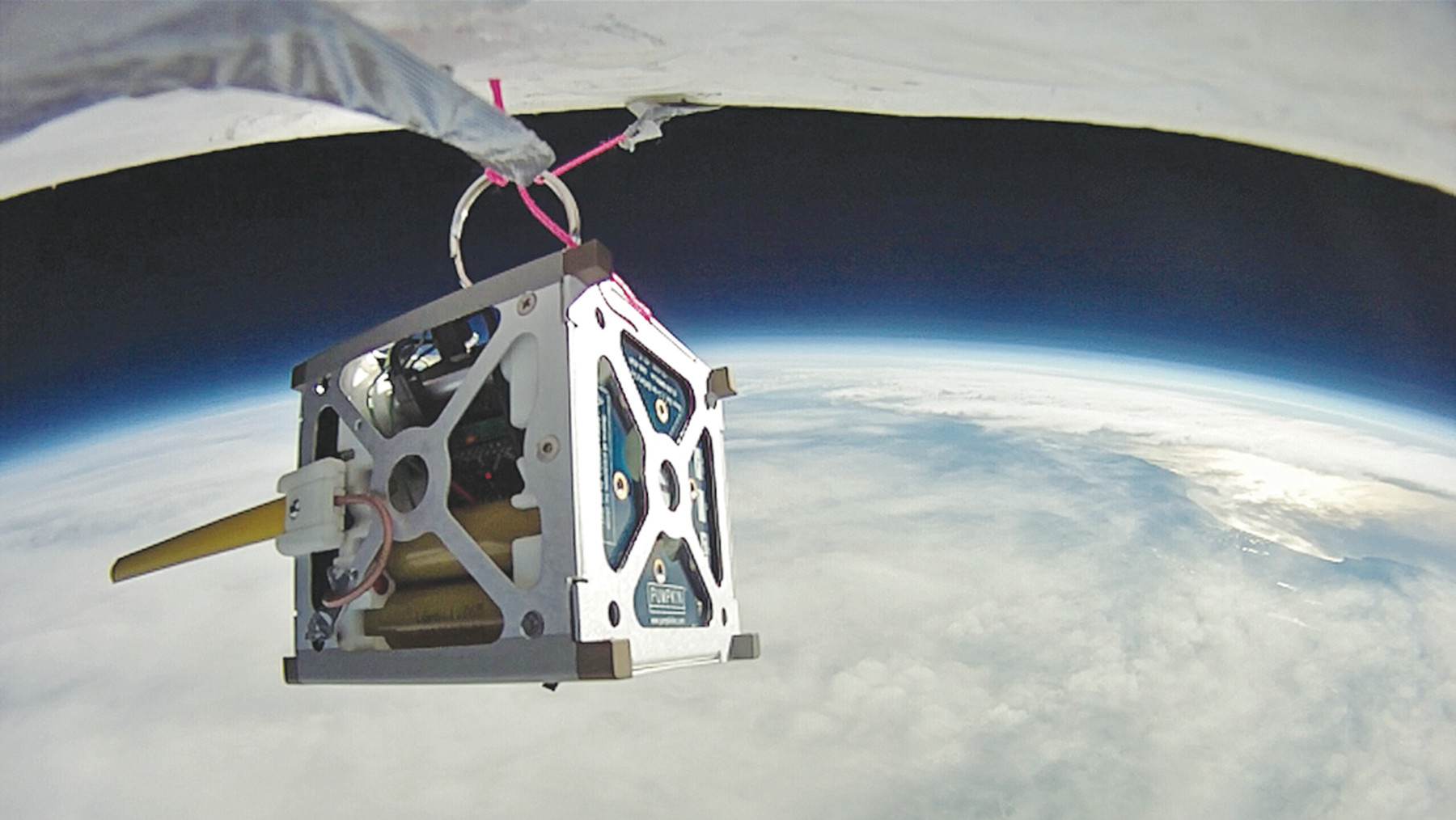2012.10.12
Foreign Affairs誌より─ニール・ガーシェンフェルドの「ほぼ、なんでも作る方法」

Foreign Affairs誌に、ニール・ガーシェンフェルド(Neil Gershenfeld)のHow To Make Almost Anything(ほぼ、なんでも作る方法)という長い記事が載った。このタイトルは、ガーシェンフェルドのMITでの有名な講義から来ている。このクラスの過去の名簿を見れば、知っている名前がたくさん出てくる。Formlabs、David Cranorと Maxim Lobovskyもそうだ(彼らは先日のMakr FaireでForm 1プリンターを初披露してくれた)。
この記事の導入部分を抜粋しよう。
新しいデジタル革命が起ころうとしている。今回は製造分野だ。この革命の形には、初期のコミュニケーションとコンピューターのデジタル化を推進したかつての展開が重なるが、今回そこにプログラムされているものは、仮想上のものではなく現実の実体だ。デジタルファブリケーションでは、いつでも、どこでも、必要なときに、個人でデザインして、手に取って触れる実体が自由に作れるようになる。こうしたテクノロジーが広く普及することで、既存のビジネスモデル、海外支援、教育は変貌する。
この革命のルーツは1952年にさかのぼる。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者たちが初期のデジタルコンピューターをミリングマシン(フライス盤)と接続して、初めて数値的に制御する工作機械を作り上げたときだ。金属のブロックを移動させるために機械工がハンドルを回すかわりに、コンピュータープログラムがそれを行う。手でやるよりも複雑な飛行機用の部品を削り出すことに成功したのだ。この革命的な最初のエンドミルに始まり、あらゆる種類の切断ツールがコンピューター制御式プラットフォームに取り付けられるようになった。研磨剤を含む水のジェット水流で固いものを切断したり、レーザーで細かい細工を即座に切り出したり、電気を流す細い線で長くて精細な切断を行うといった具合だ。
今日、数値制御される機械は、直接(ノートパソコンのケースやジェットエンジンなどの部品を作る)、間接(大量生産品の鋳型や押し型といったツールを作る)を問わず、 ほとんどすべての商業製品に関係している。ところが、最初の数値制御機械の子孫たちには、最初から存在した共通する制約があった。切断はできるが、内部構造を作ることができないという点だ。つまり、たとえば車輪の車軸は、それを通すベアリングとは別に作らなければならないということだ。
しかし、1980年代にコンピューター制御による製造で、素材を削り取るのではなく、継ぎ足せるもの(加算的製造(additive manufacturing)という)が市場に登場した。3Dプリンターによって、車軸とベアリングが同じ機械で同時に作れるようになったのだ。今や、いろいろな形式の3Dプリントが利用できる。プラスティックの糸を熱して融合させる方法、架橋ポリマーレジンに紫外線をあてる方法、接着剤の粒で粉を固める方法、紙をカットして重ねる方法、金属の粒にレーザーをあてて融合させる方法などだ。ビジネス界では、製品を作る前に3Dプリンターを使ってモデリングすることがすでに始まっている。こうした工程をラピッドプロトタイピングと呼ぶ。また、宝飾品や医療用のインプラントなどの複雑な形状の製品を作る企業でも、こうした技術に頼るようになっている。研究施設などでは、3Dプリンターを使って細胞から構造体を作る研究をしている。目標は生きた組織を作ることだ。
加算系製造は、革命として広く称賛され、Wired誌から The Economist誌まで、雑誌の表紙を飾るようにもなった。しかしこれは、当事者よりも周囲の人間が喜んでいるという面白い種類の革命だ。設備の整った工房では、3Dプリンターを使った作業は全体の1/4ほどにすぎず、残りの3/4は他の工作機械で行われる。なぜなら、3Dプリンターは速度が遅く、ひとつのものを作るのに、数時間から、ときには数日かかることもあるからだ。その他のコンピューター制御の工作機械を使えば、より高速で、より高精度に部品を作ることができる。また、より大きく、より軽く、より強いものが作れる。3Dプリンターに関する熱狂的な記事は、電子レンジが未来の調理器具だと称賛した1950年代の記事を彷彿とさせる。電子レンジは便利だが、他の台所用品に取って代わるものではなかった。
これは、加算的と減産的の製造方法の対決という革命ではない。データを物に変換する能力と物をデータに変換する能力の革命だ。それがこれから起こることだ。ひとつの観点から見ると、それはコンピューターの歴史に類似している。その発展過程の最初のステップは、1950年代に大型のメインフレームコンピューターが登場したときだ。それを使えたのは、企業、行政、選ばれた研究機関だけだった。次は1960年代のマイクロコンピューターだ。これは、MITで初めてトランジスター化されたコンピューター、TX-0をベースに開発されたデジタルイクイップメント社のPDPファミリーによって先導された。これにより、コンピューターのコストは十万ドル単位から一万ドル単位に低下した。個人で買うにまだ高すぎたが、研究所や大学や中小企業でも購入できるようになった。このデバイスを使っていた人々が、電子メールを送る、ワードプロセッサーで文章を書く、ビデオゲームで遊ぶ、音楽を聞くといった現在のコンピューターのほとんどすべての用途を開発した。マイクロコンピューターの次がホビー用コンピューターだ。なかでももっとも有名なMITS Altair 8800は、1975年に、完成品で約1,000ドル、キットで約400ドルという価格で発売された。その能力はごく基本的なものだったが、コンピューターの黎明期世代の人生を一変させた。個人でコンピューターを所有できるようになったのだ。最後に、1981年、IBMのパーソナルコンピューターが登場して、コンピューターは完全にパーソナルになった。比較的コンパクトで、簡単に使えて、便利で、価格も手の届くものだった。
昔のメインフレームと同じように、初期のコンピューター制御式フライス盤は、大きくて高価で、一部の施設にしか導入できなかった。それが1980年代になると、ラピッドプロトタイピングシステムの最初の世代が、3d Systems、Stratasys、Epilog Laser、Universalといったメーカーから発売され、価格も十万ドル単位から一万ドル単位に引き下げられた。これは研究機関の興味をひいた。次なる世代のデジタル製造機器は、現在、市場に出回っている。RepRap、MakerBot、Ultimaker、PopFab、MTM Snapといったメーカーの製品だ。価格は数千ドル単位だが、部品だけ買えば数百ドルだ。これまでのデジタル製造機器とは違い、これらの製品は設計図が無料で公開されている。そのため、道具さえあれば(ホビー用コンピューターなど)、これを使うだけでなく、自分で作ったり、改造したりができる。パソコンに相当する統合的なパーソナルデジタル製造機器はまだ現れていないが、いずれ現れるだろう。
パーソナルファブリケーションは、SFでは欠かせない小道具として何年も前から存在していた。テレビシリーズの「スタートレック:ネクストジェネレーション」では、とくに挑戦的なストーリーが展開されていた。彼らは船内に装備されたリプリケーターで、なんでも好きなものを作ることができるのだ。数多くの研究所の研究者たち(私も含む)は、現在、その本物を作ることに取り組んでいる。個別の原子や分子を操作して、望みの構造に並べるという工程の開発だ。現在の3Dプリンターと違い、完全に機能するシステムを一度に作ることができる。部品を組み立てる必要もないのだ。その目的は、単に無人飛行機の部品を作るというようなことではなく、プリンターから取り出せばすぐに飛べる完全な飛行機を作ることだ。完成までにはまだ何年もかかるが、それを待つまでもない。今みんなが使っているコンピューターの機能のほとんどは、パーソナルコンピューターが花開くずっと前の、マイクロコンピューターの時代に生まれたものだ。同じように、今日のデジタルファブリケーション機器がまだ幼年時代だとしても、すでに、どこででも、(ほぼ)あらゆるもを製造できる。それがすべてを変えていくのだ。
記事の全文は、Foreign Affairs誌のサイトでどうぞ(英語)。
– Shawn Wallace
[原文]