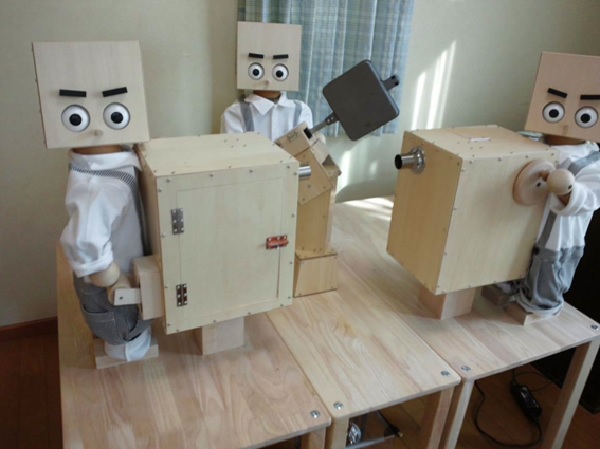2018.08.31
Maker Faire Tokyo 2018レポート #9:パネルディスカッション「オルタナティブ・ライフ:まだ見ぬ生命の姿を求めて」
例年よりさらに会場面積が拡がったMaker Faire Tokyo 2018。イベントが開催されるステージもセンターステージのほか、Makerステージ、ライブステージ(DIY MUSIC)、教育イベントスペース(Make: Classroom)が設置され、多数のトークやプレゼンテーション、パネルディスカッションが実施された。2日間、常時どこかでMaker向けの技術紹介、起業や企業内Maker活動についてのディスカッション、海外事情レポートやハンズオン、ライブが行われているプログラム。各ステージには多くの来場者たちが時間をチェックしながら目当てのイベントに駆けつけていた。
そのようなプログラムの中でも、とりわけ注目を集めたのが2日目のパネルディスカッション「オルタナティブ・ライフ:まだ見ぬ生命の姿を求めて」(8月5日 14:30〜)である。Maker Faireでは異色とも言えるこのプログラム。当日のパネルの内容を紹介しよう。
このパネルが開催されたきっかけはまず、モデレーターの久保田晃弘氏(多摩美術大学情報デザイン学科 教授)が、『バイオアート』(ビー・エヌ・エヌ新社)という書籍の監修とプロデュースを手がけていることがある。パネラーのドミニク・チェン氏(早稲田大学文化構想学部 准教授)は、共著書『作って動かすALife —実装を通した人工生命モデル理論入門』(オライリー・ジャパン)を7月に刊行したばかり。もうひとりのパネラー、津田和俊氏(山口情報芸術センター[YCAM]研究員)は、監訳を担当する翻訳書『BioBuilder(バイオビルダー)』(オライリー・ジャパンより近日刊行予定)の刊行を間近に控えている。
それぞれの書籍に通底するテーマとして、「生命(Life)」と「(自分で)つくる(Make)」ことがあり、内容には人工生命(ALife)、合成生物学といったこれまでは専門的な領域に属していた知識や技術が個人のMakerにも手がけられるレベルに熟してきていることが反映されている。人工生命の歴史やモデルの概念、実際のシュミレーションを紹介するのが『ALife』で、合成生物学の概念と実験演習を紹介するのが『バイオビルダー』だ。
交差するコンピュータ科学と生命科学
冒頭で久保田氏は、2010年に人工細胞の合成に成功したクレイグ・ベンターがそれを発表した際のビデオを紹介した。そしてこう続ける。
久保田「このビデオの面白いのは、いかにして人工細胞を作ったかが語られるところ。つまり、合成生物学の話です。その細胞には、自分たちが作ったものが自分たちのものであることがわかるようにウォーターマーク(デジタル透かし)を入れたり、設計のチームメンバーの名前を入れたりした話が続きます。その話で、僕らは思い出すんです。1984年に発表された、初代Apple Macintoshの筐体内部にも設計者のサインが入っていたことを。つまり、技術的にも文化的にもコンピュータと生命科学は似ているところがあって、現在も交差しているということです」
次に、2016年3月に、J・クレイグ・ベンター研究所(JCVI)から発表された最小のゲノムを持つ生物「JCVI-syn3.0」の写真が映された。
久保田「プログラムをGitHubでダウンロードするように、このVer.3.0のゲノムはダウンロードすることができます。だから、同じものを個人が作ることができる。そんな風に言うと『口で言うほど簡単じゃない』と専門家からは言われるわけですが(笑)。ただ、かつてはコンピュータも研究者や政府のもので“高嶺の花”でした。マイクロプロセッサの登場により、ホビイストが作れるようになったわけです。そして今や、こんなスマートフォンになっている。そこを思えば、この先人工生命や合成生物学はますます重要な意味をもって僕らの日常生活に影響を与えてくるのではないか、と考えられるわけです」
また、「生命」という言葉の捉え方については、メディア理論家のレフ・マノヴィッチの言葉が紹介された。
実際、「写真」というものなど存在していたのだろうか? タルボットの1830年代の塩化銀の写真、レンズを使わなかったマン・レイの1920年のフォトグラム、そして動いている被写体に自動的に焦点を当てるカメラが1/8000秒で撮影した現代の50MPの写真の間に、何か共通のものはあるだろうか?(さらに今では、1秒間に5兆フレーム撮影することができる、科学用に開発されたカメラまである)—— レフ・マノヴィッチ『インスタグラムと現代イメージ』
久保田「『写真とは何か』もけっこう難しい問題でして、どんな写真もひと口に“写真”と表現すると何も見えなくなるところがあります。けれど、例えばインスタグラム、そこに着目することでクリアになるものがある。とすれば、生命という定義はものすごく広いのだけれども、コンピュータで作る生命、合成生物学で作る生命と、フォーカスを絞ることによって『生命とは何か』の議論が深まる可能性があるわけです。まずは作ってみることでわかることはとても大きいはずで、今日はそこの話をしたいと思っています」
人工生命は“作って動かす”ことで進展する
久保田氏の話を受け、ドミニク氏の話も、コンピュータと人工生命の歴史から始まった。まずは、MITメディアラボを創設したニコラス・ネグロポンテ。彼は90年代に「Being Digital」「From Bits to Atoms」と語り、ちょうど20年後に「Bio is the New Digital」と語っている。「20年の間にこう変化するところが、先ほどのコンピュータと生命科学の交差という話にもつながる現在の状況の面白さ」と、ドミニク氏。
次に、『作って動かすALife』で取り上げられ、GitHubで公開されている人工生命モデルのサンプルプログラムが画面とともに紹介された。
・ニューラルネットを内部状態として持つ蟻のシミュレーション
・鳥の群れのシミュレーション「ボイド」
・ロドニー・ブルックスが考えたサブサンプション・アーキテクチャからのモデル
・生命のパターンの発現をもたらすチューニング・パターン
・生命の本質は自己増殖性にあると考えていたヴァレラが作ったSCLモデル
ドミニク「本では、1950年代の歴史的なモデルからおおよそ80年ぶんくらいをカバーするモデルをサンプルとして取り上げています。ALifeの長いようで短い歴史の中でやってきたことは、コンピュータを使ったり、ロボットを作ったり、細胞を作ったりすることで、生命の特徴を再現してみることです。初期の生命のパターンの生成は、セルラーオートマトンで表現されたりしました。個体としての生命は、生化学的な実験で形成が試みられたり。個体がどう維持され、どう複製され、どう自律性を持つか、そして個体と個体は相互作用し、集団形成し、さらに進化していくという流れの中、それぞれの特徴や段階におけるパーツの研究がALifeでは行われてきたわけです。しかし、これを全部まとめるものは、まだできていないんです。つまり、ALifeはまだ進行中の学問領域で、その方法や理論は、これから作りながら考えていくしかないんです」
そして話は、もう一度コンピュータの歴史に戻る。
ドミニク「みなさんご存じのように人工知能(AI)が技術的な表舞台に出てきた時には、アラン・チューリングとフォン・ノイマンという立役者がいました。ふたりは同時に生命現象にも強い興味を持ち、チューリングは前述のチューリング・パターンで化学反応を数式化、さまざまな生命のパターンが数理的に作れることを1950年代に発表しています。この本のサンプルコードを使うと、パラメーターを変えて例えばこんなパターンが作れます。実はこれ、海洋生物学ではノウサンゴというサンゴのパターンに構造的に類似するのですね。そんな生命との相関が、チューリングから50年を経て後付けでわかってきています。フォン・ノイマンが考えた自己複製オートマトンは、コードが自分自身をどうやって複製できるか、自己複製という生命の特徴をコンピュータで実現させようとしたものです。60年代に考えられたのですが、当時はマシンパワーが足りず、動かせるようになったのは2000年代になってからです」
80年代にクリストファー・ラントンが、「Artificial Life(ALife)」と名付け、ソフト、ハード、ウェットといったウェアを使っていく人工生命の学問分野は成立した。最近では、アートや哲学の面からも人工生命が追求されつつあり、その実例として今年日本で開催された国際会議「ALife2018」のプレイベントで公演されたアンドロイド・オペラ『Scary Beauty』のビデオが紹介された。
ドミニク「一方、これまでは研究者なら常識とされているアルゴリズムや知識が、実際にウェブプログラミングをやっている人、クリエイティブコーディングをやっている人まで降りていなかったんですね。人工生命という学問領域が一般に周知されていくためにも、今回のような本が必要だったということもあります」
工学の「抽象化」「標準化」を応用する合成生物学
山口情報芸術センター[YCAM]研究員である津田和俊氏は、YCAMにあるバイオラボ、現在手がけている『バイオビルダー』の内容を紹介した。この本は、合成生物学、バイオデザイン、DNA工学の基礎がわかり、DIYの領域の中で実践ができる本であるという。
津田「『バイオビルダー』という言葉は、まだ耳慣れないかもしれません。これは、ログビルダー、レゴビルダーと同じニュアンス、“生命を構築していく人”の意味でこれから定着していくかもしれない言葉です。DNAは、ひも状の二重らせんの物質です。ATGCという4つの構成要素でなっていて、その配列によって遺伝情報を伝達していきます。コンピュータと生命科学の行き来という話がありましたけれども、ひも状の物質であるDNAから情報をひも解き、読み・書き・編集することで進化させていくのが、合成生物学の本質です。合成生物学の目的(ゴール)は、設計図であるDNAを編集して、仕様通りに振る舞うものを作ろうとすることです」
今日の合成生物学は、DNAの一部を設計、編集し、そのDNAを既存の細胞や生き物と組み合わせていく。新しくできた細胞あるいは生物は、設計された仕様にしたがって振る舞うようになる。その合成生物学には、工学の手法が応用されており、具体的には「抽象化」や「標準化」だという。
津田「抽象化では、工程を階層に分けてざっくりした設計からどんどん細部を詰めていく手法が使われます。まずはブラックボックスとしておいて、中味をどんどん詰めて実装していくというのは、実は工学やものづくりではごく当たり前のことですよね。もうひとつの標準化では、環状のDNA(プラスミド)を編集していく時に、組み込む要素を規格化しています。その要素は『バイオブリック』と言われていて、標準化されて互換性のあるバイオブリックにより、機能が実現されていくことになります」
本で紹介されている実験演習の例として、大腸菌を使った実験の実際も見せてくれた。
津田「大腸菌はよくバイオラボで使われるのですが、大腸菌はにおいがきつい。それでよいにおいのする実験室にしたいと学生たちが提案したのが、バナナの香りがする大腸菌への改変です。ドミニクさんの本は実際のコードを動かして体験してみるということでしたが、この本も体験のためのキットが用意されていて、オンラインで購入することができます。私たちもキットを輸入、実験をしてみました。バナナの香りの大腸菌ができましたよ。その詳細については、日本語版で紹介していく予定です」
各領域の接続と相互作用で生まれていくもの
久保田「これまでのお話で、『作って動かすALife』が、GitHubからコードをダウンロードでき、それはオープンソースなので自分でどんどん改善して試していけるようにまとめられていることがわかりました。また『バイオビルダー』が、実際の体験キットで実験できる教則本のようなものであることがわかりました。ここで、もう一度、最初にした質問をおふたりにしたいと思います。これらの本を通してどうでしょう? 改めて『生命って何だろう』と考えたのではないでしょうか?」
ドミニク「人工生命の領域でも『これが生命である』との定義には至っていません。しかし、年々フォーカスは変化してもいて、現在ホットなトピックは『Open-ended Evolution』、つまり目的の定まっていない、開かれた進化です。例えばAIなら、ビジネス展開に向けた考え方として目的を定め、そこにどう到達できるかを突き詰めるわけですが、それとALifeは似て非なるところがあります。そもそも進化をはじめとする生命現象はオープンエンドなもので、そこに人間がどう向き合えるのかなのですね。そこの議論は、既存の専門分野以外の人や知識も取り入れないとなかなか深まりません。つまり、領域自体がオープンエンドに進化していく必要があるのだと思います」
久保田「もしかすると、『生命を作る』というテーマのほかに『生命を移植する』というような、そんなこともあるのですか?」
ドミニク「それはこちらでは『生命性を実装する』と言いますね。ALifeの適応先はかなりあります。例えば僕たちが触れ合うコミュニケーションソフトはスマホにもありますけれど、そこにALife的な生命性を実装したらどんな設計になるのか。それはバーチャルロボットやペットロボットみたいなものかもしれません。現在入っているのはAIですが、ALifeエンジンみたいなものが実装されていくかもしれないです。ALifeにもAIの技術は多く応用されていて、かなりかぶっているのですけれど、設計思想の原理的な違いはいったい何か、そのような議論もされているところです」
久保田「なるほど。津田さんのほうではいかがですか? 例えば子どものころに昆虫採集をしたり、お祭りで金魚すくいをしたりしますよね。そんな記憶では生命はかなり生々しくあるものです。そうした伝統的に培ってきた生命観、それは合成生物学を通していくと強化されるのか、希薄になっていくのか、そこが僕は素朴に気になるのですが」
津田「合成生物学はまず、DNAを読むことからはじめることになります。そうすると、自分の身体の中のDNA、昆虫にしても動物にしても植物にしても微生物にしても、すべての細胞にDNAが入っていて、そこから設計されるものとして生物があること、その事実に気づくのですね。これはまったく当たり前のことなのですけれど、かなりの驚きにつながるんです。今日ここにはものづくりをしている人が多いと思います。同じような設計ですべての生物が、自分たちも含めてできあがっていること、そんな“設計可能な”生命であることの事実。そこを発見するのはやはり驚きですし、興味の尽きないところになるんです」
久保田「大腸菌の実験やALifeのモデルを見ていたら、僕は、セルオートマトンの動きをする大腸菌を作ったら生命の起源がわかったりするのか、なんて思いましたけれど(笑)」
ドミニク「そんなインタラクションが面白いんです。僕は発酵食が好きでぬか床を10年以上育てているのですが、やっていると微生物に対する解像度が上がってくる気がします。つまり、何がどうなっているかの知識が増えて、身体感覚が身に付いてくるんです。いつしか僕は菌の言いなりになって、拭いたり仕込んだりするようになる。どっちが制御しているのか、制御されているのか、わからなくなる(笑)。そんな相互作用が起こります。ALifeも、生命を完全に制御するのが目的ではなくて、自律的に対峙する存在としての生命を作り出すことでわれわれ自身がどう活性化していくか、そんな次元に来ているのかなと僕は思っています」
津田「そうですね。人工生命や合成生物学というと、生命を“制御する”ものと捉えられがちです。またそのことによって倫理的な批判もされるわけです。実はそうではなくて、生命への理解を深めること、それが第一なのだと思います。システムとしての生命を制御すると考えるのであれば、システムには入力があって出力があるわけですよね? これはコンピュータも同じ。しかし、コンピュータと生命が決定的に違うのは、ひとつのインプットにひとつのアウトプットが対応するのではないことです。生命の場合、入力にも出力にもさまざまな要因がからみます。そこには多様な反応があり、意識も生まれて思考もして、結果としての動作がなされていく。それが生命なのだと思います」
個人のものづくりや市民ラボでの活動がAIや合成生物学といった新たな科学領域へ拡張できるようになってから、まだ日は浅い。しかし、手元で作り、動かし、実験をすることが、生命科学の本質に迫る可能性があるという話は、おおいに興味をかき立ててくれるところだ。Makerとしてこれらの分野に注目し、接続してコミットしていくことに意義や期待があることも強調されたパネルディスカッションだった。