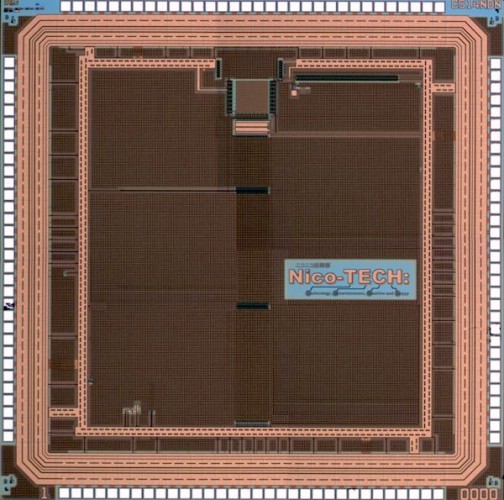編集者より:Matt Lorenzのユニークな音楽作品「The Suitcase Junket」を見て聞いた我々は、すっかり魅了されてしまった。そこで、彼の経歴、何に影響されてこのような活動を行っているのか、どうやってこの素晴らしい作品が生まれたかについて話を聞いた。そのすべてをお届けしたい。
Swamp Yankee(スワンプ・ヤンキー)という言葉を初めて聞いたとき、自分もそうなのかと尋ねられた。そしてこう思ったのを覚えている。「自分もスワンプ・ヤンキーでありたい……、でも、スワンプ・ヤンキーってなに?」。私は模範的現代人として、すぐにググり、その意味を確かめた。広い意味では、北部の田舎者ということだそうだ。よし、私はバーモントの山の中で育ったし、当てはまってる! それ以来、私はこの名前を自分の作品の旗印にしている。どんな音楽をやっているのかと聞かれると、「スワンプ・ヤンキー・ミュージックだよ」と答える。あたかも、それが確立されたジャンルであるかのようにね。しかし、音楽のスタイルという以前に、それは私の創造的探求のための指針であり、指標でもある。価値観みたいなものだ。手持ちの材料で必要なものを作る。身の回りのものを集めて、それを欲しいものに作り変える。ヤンキーならではの創意工夫の力と強固な独立心でもって、物質世界からかき集めたものを、機能的で美しい品物に変化させるのだ。
私は子どものころ、電話機を分解することと、自分で自分の髪の毛を切ることの許可を得ているとベビーシッターを説得したことがあった。電話は二度と元に戻らなかった。そしてそれから数週間、私はフィル・コリンズのような頭で過ごすことになった。その後、何年間も私はものを分解し続けた。ラジオ、電話機、テレビ、オルガン、腕時計、虫、本、自転車、ボイラー、人間関係。元に戻そうとか、直そうという気は一切なかった。どういう仕組みになっているのかを知りたくて分解したあと、その部品を使って別のものを作ることもあった。当時の子どもの頭では、ものを分解し続けることで、あらゆるものは(自然も含め)人間が作ったのだと信じるようになった。私も人間なのだから、理論上、あらゆるものが作れるはずだと思い込んだ。単純な「気づき」だが、それは強烈だった。私の子ども時代の信念は「自分でやる」だ。それは今でも変わらない。今でも自分の髪は自分で切っている。大惨事になることもあるが。
お金がなかった時代から、バケツと缶との愛に満ちた関係が長く続いている。チェロが欲しかったのだが、そんな高級品を手に入れる術はなかった。私は畑を耕したり、家のペンキを塗ったり、歌を書いたりして金を稼いでいたが、すべては食べ物と家賃と借金(アメリカンドリームだ!)の返済に消えた。ある日の午後、ゴミ捨て場を歩いていた私は、金属ゴミ置き場を覗いて激しい創造状態に陥った。ゴミを捨てに行ったはずなのに、捨てた以上のゴミを持って帰ってきた。そこから一弦のバイオリンをいくつかと、松葉杖と薬棚でベースを作った。音は最高だった。荒削りだが、心に残る美しさがある。必要なものは、硬い棒と弦とチューナー(通常はアイボルトを使うが、ギターから外したペグを使うこともある)、それに、弦の振動を伝えるブリッジと音を共鳴させる役割を果たす缶や箱だ。私は天国にいる気分だった。それは魔法だった。
古い銅管と水やり用のホースで管楽器も作った。瓶の首でマウスピースを、コーヒーの缶でベルを、キッチンの流しでチューバも作った。声はメガホン型のアンプで拡声する。そしてもちろん、ドラムだ。小さなドラムがあちらこちらにある。自分で楽器を作ったことで、ごく未熟ではあったが、私はそれから数年間、奇妙な曲をたくさん録音した。だが、ハードディスクの中に蟻が浸入して巣を作ってしまい、全部ダメになった。簡単に手に入るものは、簡単に消えていく(蟻に手を出すことはできない。彼らは我々よりずっと優れているのだ)。
このプロジェクトにより、ゴミ置き場には素晴らしい材料が毎日捨てられてることを知り、私はゴミ置き場の虫となった。その夏、壊れた自転車の山を発見した。そのほとんどがコミュニティサイクルで使われていた自転車で、フレームが激しく折れ曲がっていた。私は、ギヤ、チェーン、ブレーキケーブル、リム、フォーク、フレームなど、回収できる部品を集めて持ち帰り、フランケンシュタインのような自転車を組み立て、友だちやご近所さんに販売した。たしか、実際に販売したのは2台だけで、残りはタダでゆずってしまったはずだ。そのプロジェクトに飽きてしまったからだ。少し後になって、余った部品を使ってアップルサイダーを作るためのリンゴの搾り器を作った。
もうひとつ、上出来だった作品に、カエデの樹液からメイプルシロップを作るための鍋の火炉として、古い50ガロンのドラム缶を切断して溶接したものがあった。私はそうした精神の心を奪われた。ものが捨てられるのを見るのが嫌だった私は、そのころ、材料をせっせと集めていた。ただ貯め込んでいるだけだと言われるかも知れないが、それぞれの廃棄物の山ごとに、私は心の中で何にするかを決めていたのだ。美しいもの、そして便利なもの、できれば美しくて便利なものを作ろうと考えていた。
その日暮らしだった当時、私は酒も自分で作ろうと思い立った。作ったのは、ほとんどが蜂蜜酒とカントリーワイン、メテグリン、メルメロ、そしてときどきビールだ。コンロの上に載せて使う蒸留器があったかもしれない(あれ、まだ違法だったの? どうして?)。山に入ってベリー類や花をたくさん採ってきて売っては、砂糖や蜂蜜を買う金に充てた。将来は死ぬほど飲めるという約束のもとに、友だちから寄付を集めたこともあった。
この酒作りは、魔法と神秘と変形を求める私の一部を満たしてくれた。窯で煮え立つ酒の前に立つと、私は偽科学者の気分になれた。この実に単純なプロセスで、水が、香りのいい甘い酒に激変するのだ。ゴミから楽器を作るときと同じ魔法が働いている。ゴミとして山積みされていた缶やバケツをちょっといじると、生命が吹き込まれて音を鳴らすようになる。何も言わなかった空き缶の口から、心に響く歌や感情がメロディーに乗って流れ出すようになる。拾ったものに歌を歌わせる。それが私の世界観となった。
現在は、「The Suitcase Junket」(物見遊山)という音楽プロジェクトに集中している。自分の足で自作の缶ドラムを叩き、ゴミ捨て場から拾ってきたギターと、小さな骨やナイフやフォークが入った箱(ご想像どおりの音がする)と、丸ノコの刃と小さなガラクタのキーボードを鳴らして、一人で演奏している。私は国中を、そして世界を旅して、ゴミの山から生まれた歌やサウンドを届けては、いろいろな考え方や指抜きや空き缶やリズムや不安や驚きを集めている。
私は遊び心と好奇心が大好きだ。冬の終わりには今でも、ドラム缶で作った炉を使って家の前でメイプルシロップを煮詰めているし、自転車の部品と薪で作った道具でリンゴを搾っている。また時間があるときは、工事現場で拾ってきた古い「木ずり」で大きな羽根の彫刻を作っている。さらに1年に1度は、小学校2年生の生徒を集めてゴミから楽器を作るワークショップを開いている。
私は、他の人の手に渡る前に、あらゆるもの(歌や考え方も含め)の可能性を考えるようにしている。捨てられたものを拾い集め、形を変えて、また世界に戻してやる。私たちは終わりのない消費と廃棄の文化の中で暮らしている。私も間違いなく、そのシステムに加担している。これは、私自身とその他の人々の関心を、私たちは十分にものを持っているという考え方に向けさせる1つの方法だ。必要なものは、すべて身の回りに揃っているのだ。
[原文]