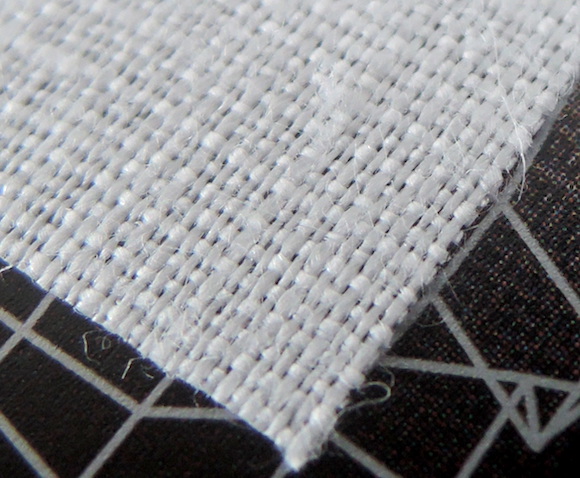テクノロジーの普及がものづくりの場やそのプロセスを変えつつあるのと同時に、テクノロジーを人と人の生活の中に根ざすものにしようとする流れがある。テクノロジーを駆使して作られたプロダクトやサービスを使うのではなく、「食べる」や「遊ぶ」といった、人が普通に行うことにテクノロジーを活かす。全国各地に存在するファブ施設やアートセンターは、現在、後者のような活動も含めて、新しいテクノロジーに向き合っている。
YCAMスポーツハッカソン2018&第3回 山口の未来の運動会(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])
山口情報芸術センター[YCAM]は山口市を拠点に、アートとテクノロジーを組み合わせた展示やワークショップなどを積極的に展開しているアートセンターだ。展示やワークショップのためのスペースはもちろん、アーティストやクリエイターが制作する環境、研究開発のための設備がそろっている。特徴的なのが、図書館や映画館といった一般の市民が出入りする場所が建物の中でひとつにつながっていること。
YCAMが活動の柱としているものが3つある。
・メディアやテクノロジーと市民をつなぐ
・YCAMでなければ生み出せないオリジナルな作品づくり
・YCAMのノウハウや知見を地域に結び付ける
「メディアやテクノロジーと市民をつなぐ」プログラムとして行われているのが、YCAMスポーツハッカソンだ。2018年5月、3回目となるYCAMスポーツハッカソン2018&未来の山口の運動会が行われた。
スポーツを作る
スポーツハッカソンにデベロップレイヤー(「デベロッパー」と「プレイヤー」を合わせた造語)として参加する参加者は、5/4-5/5の2日間で新しいスポーツを作り、5/6に行われる「未来の山口の運動会」に参加する人たちと一緒に、その新しい種目を実際に体験してみる、というのがイベントの概要だ。
種目(競技)は、運動会で実施することが前提となる。運動会では、300人の参加者を4つのチームに分け、対抗戦で勝敗を決める。それに応じて、およそ30人のデベロップレイヤーは4つのチームに分かれて新しい種目を作るのだが、アイデア出しから始めて「作りたいもの」の投票を行う。いわゆる一般的なハッカソン、アイデアソンと同じだ。
おもしろいデザインだなと感じたのは、アイデアを着地点に向けグルーピングすること。たとえば「全員参加の種目」、「選抜で行う種目」、「勝敗を付けない種目」といったように分類する。実際に行うにあたって、300人が全員参加するのはなかなか難しい。かといって、選抜だけではどうしても競技に参加するメンバーが偏ってしまう。そこで、大まかにではあるが、最初からバランスを取れるよう分けておくのだ。
この大枠があれば、アイデアを机上で取捨することに重きを置かなくて済む。大枠に収まっているのであれば、是非を口頭で議論するより、まず試してみようという流れになる。アイデアを「ふるう」手間を省き、時間がある限り、試して、ブラッシュアップして、仕組みに落とし込んでいく。
さらに、YCAM内部に設置された研究開発チーム「YCAMインターラボ」のメンバーがデベロップレイヤーの一員として必要な限りプログラムを書く、ハードを動かす仕掛け部分を作るという実作業の部分を全面的にバックアップすることで、「試す」と「ブラッシュアップ」を早いスパンで回すことが可能になっている。
![チームごとに作ることにした種目をプレゼンする(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])](https://makezine.jp/wp-content/uploads/2018/06/DSC2182_edited.jpg)
チームごとに作ることにした種目をプレゼンする(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])
つまり、およそ30名のデベロップレイヤーは、2日間(正確には1日半)で300人が参加する運動会の競技種目をまったくのゼロから作り、最終日は、実際に種目を行い、300人を楽しませる。そのための「アイデアを出す」→「アイデアを試す」→「完成させる」ことに集中できるのだ。
![実際に試しながら、ルールに落とし込んでいく(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])](https://makezine.jp/wp-content/uploads/2018/06/DSC2560_edited.jpg)
実際に試しながら、ルールに落とし込んでいく(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])
アイデアソン、ハッカソンでよくあるのが、「最初のアイデアにこだわって発展する可能性をつぶしてしまうこと」であったり、「アイデアが発散したまま収束しないこと」、「なかなかプロトタイプができあがらないこと」なのだが、それらがうまく回避されるデザインになっている。
もちろん、フリーランスのキュレーターで本イベントの企画、ファシリテーションを務めた西翼氏、YCAMのエデュケーター朴鈴子氏、さまざまな企業で社内運動会のプロデュースを手がける運動会屋の米司隆明氏、王子の遊び総合研究所所長でありゲーム監督としても活動する犬飼博士氏、ジャンル問わず年間200件以上の司会・MCを務める西垣峻宏氏ら、スポーツハッカソンにかかわっているメンバーが、全体を見て流れを作っていることが大きい。競技としてのルールの勘所(誰にでもすぐに、わかりやすく伝わる)を良いタイミングでアドバイスするのはもちろん、実際「やってみる」にはテスターの人間と展開する場所が必要だが、その交通整理までフォローする。
3日目の運動会では10種目が、およそ300名近く(運動会参加者300名強+デベロップレイヤー30名強)で実施された。
「アート」の要素が何を変えるのか
3回目となるYCAMスポーツハッカソンでの新たな取り組みが「ゲストデベロップレイヤー」の存在だ。菅野創氏、岸野雄一氏、コンタクト・ゴンゾ、3組のアーティストがデベロップレイヤーと一緒にアイデア出しから参加し、種目を作り上げるところまで行った。
その理由の1つとして、YCAMだからこそできるスポーツハッカソンとして、どう位置づけるかという課題意識があげられる。
朴:私たちは3年前からスポーツハッカソンをやってきましたが、この3年間の間に、全国のいろいろなところでスポーツハッカソンが行われるようになりました。徐々に、希少価値みたいなものが薄れてきたなという実感があったんです。そこで、アートセンターだからこそできるスポーツハッカソンってなんだろうと考えて、アーティスティックな要素を取り入れることなのかなというように思ったんです。
西氏も、ゲストデベロップレイヤーの存在は大きかったと言う。
西:岸野さんは「DJ盆踊り」などされていて、僕の中では運動会と盆踊りってすごく似ているけどちょっと違うというもので、何か混ぜてみたいなという誘惑にかられてお願いしました。菅野さんはもう何度も一緒に仕事をしているので信頼関係もありましたし、本人がスポーツハッカソン、未来の運動会に興味を持ってくれてコンタクトしてきてくれていました。実は、今回一番準備できていなかったのが、コンタクト・コンゾなんです。打ち合わせがほんとにできていなくて。これから検証したいなとは思いますが、やはりアーティストは、アイデアを出したり、実践するまでのプロセスにおいて、独自の、確立した考えを持っている人たちなので、彼らの存在は大きかったと思います。三者とも、個性の出方がおもしろかった。直接ではないんですが、種目に彼ららしさが出ていた。アーティストが入るとこういうふうになるんだというのが、すごく興味深かったですね。
これは朴氏も指摘しているが、アーティストの「らしさ」が種目に加わるとはどういうことかというと、たとえば「痕跡を残すな!テクノスネーク」(以下、テクノスネーク)という種目を例にしよう。
テクノスネークはチーム全員で1列を作り、前の人の肩を持って前進する。先頭の人がかぶるヘルメットがマーカーになって進んだ軌跡を描き、最後尾の人がかぶるヘルメットがその軌跡を消すというもの。2チームが対抗で同時にプレイする、途中で描く軌跡が見えなくなるなどの味付けがされて、プレイ自体に緊迫感があるわけではないのに、やっているほうも、見ているほうもスリリングな感覚を味わえるというゲームになっている。
この身体を使ったプレイ(身体が軌跡を残して、それを身体で消す)、デジタル的な仕組みを使っているのに肝はアナログというところに、身体を使った即興的なパフォーマンスを行うコンタクト・ゴンゾらしさが見える。
![実技中のテクノスネイク(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])](https://makezine.jp/wp-content/uploads/2018/06/DSC2365.jpg)
実技中のテクノスネーク(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])
コンタクト・ゴンゾの塚原悠也氏は今回のゲストデベロップレイヤーとしての参加をこう振り返る。
塚原:かなりの速度で作業しなければ、ということがあったので、完成をさせることをまず目標において、ほかにどんな人がいるのかという中で僕らはちょっと年上というのがあったし、そういう作り方は慣れているから、早い段階から、主導は僕らが取るという姿勢を出していきました。作業の配分とかしたり。同時に、別に僕らがやりたいように全部やるというわけではないということも態度で伝える、何がしたいのか、どうしたいかというのを聞いたり、というやり方でした。
彼らがテクニック、スキルの提供だけではなく、チームを自身が大きく主導していたことがわかる。初日の早い段階で集団を作り、それぞれの得意分野・特徴などがつかめれば、何をどう作るか、絞りやすくなる。
また、デベロップレイヤーから出てくるアイデアにある種の傾向が見られたと言う。そこに好き放題言ってみたり、介入していくこともアーティストの役割ではないか、と。前述のとおり、テクノスネイクには「テクノロジー主体で考える癖がない」というコンタクト・ゴンゾの作り方、これまでのパフォーマンスの経験が活かされている。
塚原:身体をどう使うかということ。それには、男女差や年齢差とかいろいろあるので、筋肉や瞬発力だけによらないことができたらいいなということから考えていきました。昔、サッカースタジアムでパフォーマンスする作品を作ったんですが、これはどういうルールの改変によって何がどう変わるかという実験でもあって、それがけっこう役立ったような気がします。サッカーとかラグビーみたいなルールを、経験者も未経験者も男女も均等にするにはどうするか。結果、均等ではないんですが。
ルールは単純、「前の人の肩を持って歩く」。それをどうすればおもしろく見せられるのか、どこにカッコよさを見出させるのか。設定を増やせば増やすほど、競技はややこしくなる。しかし、エレガントな設定が1つ、あるいは2つあれば、それでけっこう広がるゲームが作れるはずと言う。これはテクノロジーも同じだ。
塚原:逆に、不条理なこと、合理的なソリッドではないものを入れていきたいという欲望も同時にあります。これだけ1日中一緒にいたら、2回くらいドン引きさせるのが僕らの仕事じゃないかなとも思う。そういう仕掛けを入れたり、まだ可能性はあるよねというのはあります。
アートというと、絵がうまく描けたり、表現ができるなど、表面的なことが目についてしまうが、実際に重要なのは「もの」のとらえ方であり、それをどう見せるかという思考の組み立て方にある。
ただ、アーティストの個性が強く出すぎると、ハッカソンという共創の場の”感じ”が薄れてしまう。なかなか難しいところだが、今回、アーティストにデベロップレイヤーとして入ってもらうというところのさじ加減は、いろいろ学んだという西氏。YCAMスポーツハッカソンにアーティスティックな要素が加わったことによる可能性をこう語る。
西:これまではテクノロジーとスポーツでやってきたところに、アーティストが入ってきた。大げさにいうと21世紀型の総合芸術みたいになっていったらおもしろいなと思っています。オペラとか演劇みたいに、さまざまなジャンルのアーティストが入ってこられるプラットフォームみたいな感じですかね。一般的な総合芸術は作家側と鑑賞者を分けますが、鑑賞者と制作者が分かれていない状態でやる総合芸術みたいなところに発展していったらおもしろいかなと思います。
「みんながちょっとずつ変えていく」という未来の姿勢
YCAMスポーツハッカソンにはYCAM内外の多くの人が関わっている。というのも、YCAMが展開している研究開発プロジェクト「スポーツリサーチプロジェクト」からの流れと、もう1つ、犬飼博士氏と江渡浩一郎氏によるニコニコ学会β運動会部の流れ、その合流に生まれたとも言えるからだ。
ゲームクリエイターである犬飼氏は、実は、2013年に開催されたYCAM10周年記念祭でインテリアデザイナーの安藤僚子氏とともに「スポーツタイムマシン」という展示を行っている。ただ、展示は数ヶ月すると消えてしまい、なかなか復活させることができない(スポーツタイムマシンは2年後に復活した)。「じゃあ、持っているものでやればいい」と、みんなが持っている道具でやろうと始めたのが運動会だったのだ。運動会なら、みんな経験があるから、それをちょっと変えようと思える。
アウトプットとしての運動会、実際、スポーツハッカソンに参加してみて感じるのは、その部分の重要性だ。通常のハッカソンでは、プロトタイプを作るところまでがひとまずのゴールとなる。ひとまずと言ったが、もちろんプロトタイプを作ること自体がとても大変なことだ。ハード的な要素が加わると、形にするのはもっと難しくなる。
YCAMスポーツハッカソンでは、さらに、地元の人たちを迎えて運動会を実施することがゴールになる。300人を越える一般の人たちが参加する運動会は、もはやユーザーテストのレベルではなく、一種の社会実装だ。
このデザインのおもしろいところは、社会実装といったレベルまでやってしまうのに、それを持ち帰って、自分たちでやることができるところ。
スポーツハッカソンに参加し、自分たちが作った競技でおおぜいが楽しむ姿を見るという体験をしたデベロップレイヤー。そして、運動会に参加し、新しいルールの遊びを体験した参加者(プレイヤー)。それぞれが、楽しかったり、自分が生き生きとした時間を味わえた体験を持ち帰って、自分の周囲で始めることができる。
犬飼:このアイデアは、みんながちょっとずつ変えていく未来の姿勢が重要だと思っています。そして、テクノロジーを使うことが目的ではなくて、道具を使うこととそのコスト、バランスをとってデザインすることに慣れること。
いわゆる「普遍的な技術」の扱いに慣れて、まずは自分がやるんだという世代が育つことが最終的な目的なのかもしれない。
![イメージソース作の「奴隷ぐるぐる」というツールをもとに作られた競技「だるまさんがまわった」。動くセーフゾーン(緑色)からはみ出したらアウト(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])](https://makezine.jp/wp-content/uploads/2018/06/DSC3516.jpg)
IMG SRC作の「奴隷ぐるぐる」というツールをもとに作られた競技「だるまさんがまわった」。動くセーフゾーン(緑色)からはみ出したらアウト(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])
![十字の綱引きをしながら足元のセンサーを踏む「ひけひけ☆ふみふみ」(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])](https://makezine.jp/wp-content/uploads/2018/06/DSC3801.jpg)
十字の綱引きをしながら足元のセンサーを踏む「ひけひけ☆ふみふみ」(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])
![モニターに表示される文字を人が表現する「このもじな〜んだ?人文字クイズ」(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])](https://makezine.jp/wp-content/uploads/2018/06/DSC3565.jpg)
モニターに表示される文字を人が表現する「このもじな〜んだ?人文字クイズ」(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])
YCAMのスポーツハッカソンと未来の山口の運動会は、凝縮したプログラム「スポーツハッカソン for Kids」(ディレクション、コーディネートは朴氏)として、すでに2016年から山口市内の小中学校で行う授業に取り入れられている。
こうした拡がりを見せるなか、今後の目標はYCAMスポーツハッカソンと未来の山口の運動会を年に1回の頻度で開催する、恒例のイベントにすることだと言う。もちろん、イベントとして、これで完成ではない。課題として、朴氏があげるのは “作り込み” だ。
朴:スポーツのどの部分を残すべき、残さないべきといった判断が、“落ち”のところに寄っていってしまう。ハッカソンが進んでいくと思考がどんどん前に前に進みがちだから、良いアイデアやうまく整理整頓できた部分を捨てきれず、突き進んだ結果が種目になることが多い。特に子どもの場合、ただただ張りぼてなスポーツになることも。今回のような1日半しか時間がないプログラム構成上、引き下がることは大きな時間の損失にもつながるのだが、前のめりになっている思考に対して、落ち着いてふりかえるタイミングを作れないものかと思う。


![YCAMスポーツハッカソン&山口の未来の運動会(撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])](https://makezine.jp/wp-content/uploads/2018/06/DSC2462.jpg)