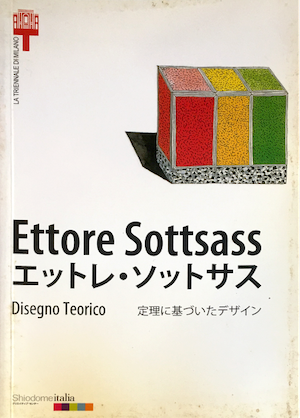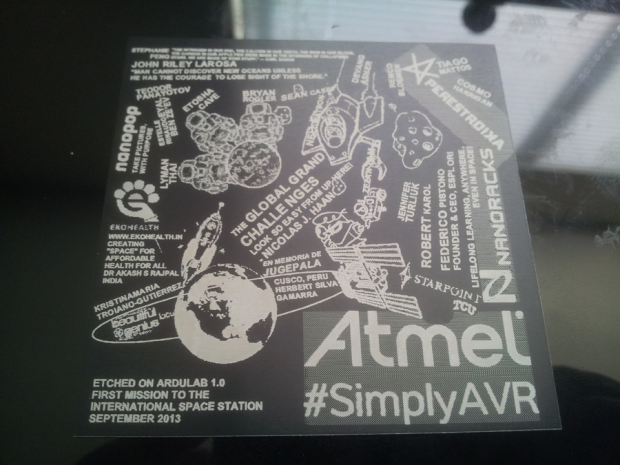本記事は、久保田晃弘さん(多摩美術大学情報デザイン学科 教授)に寄稿していただきました。
2021年5月1日にオンライン開催された、Maker Faire Kyoto 2021で、「ものづくりとユーモア」というタイトルで講演を行った。その具体的な内容については、当日の様子を収めたヴィデオや、窪木淳子さんによる丁寧なレポートを、まずは参照していただければ、と思う。そこで今回の連載では、その内容を踏まえつつ、さらに当日時間の都合でお話しできなかったことも含めて、ものごとのもつ「パフォーマティヴィティ(行為遂行性)」について考えてみたい。
講演のテーマであった「ユーモア」の始源として、18世紀の終わりから、19世紀にかけて活動した作家、ジャン・パウルの『陽気なヴッツ先生』(1973)を取り上げた。パウルは、作曲家グスタフ・マーラーの愛読書であり、その交響曲第1番に影響を与えたとされる『巨人』のような長編小説だけでなく、『美学入門』のような重厚な理論書(この本の中には「ユーモア文学について」という章もある)も数多く書いているが、『陽気なヴッツ先生』は文庫本で90ページ程度の、比較的読みやすい短編小説である。
パウルの『陽気なヴッツ先生』の岩波書店の紹介文には、
ヴッツ先生は貧しくて本が買えない。そこで有名な本の題名だけを拝借しては勝手に著述し、それをわが蔵書の棚に並べて満足感にひたりこむ。ささやかな喜びを糧に人生をおくる平凡な小学校教師の姿を、ジャン・パウル(1763〜1825)はユーモアとアイロニーたっぷりに描きだす。(後略)
とある。確かにこの内容だけでも、何やらこの本の、そして主人公のヴッツ先生のユーモラスな姿が伝わってくる。しかし僕にとって、この本のもうひとつの面白さが、それとは別のところにある。
確かに、この本の本筋、というか大きな物語は、主人公のヴッツ先生が亡くなってしまう、まさにその間際に、彼のささやかながらも幸福だった人生を、語り手としてのジャン・パウルが回想する、というものである。そこでは、外面的には取るに足らないような人生に見えても、日々の読み書きによって豊かに生きること、さらには勝手に著述するという反抗によって、幸せに生きることの可能性と喜びが、小説によって、自己言及的に宣言されている。さらに、この小説における「書くこと」「読むこと」を「つくること」「使うこと」に置き換えれば、ヴッツ先生の生涯と、メイカーの生涯が重なってくる。
ところが、そうまとめてしまう以前に、この小説を実際に読み進めていくと、そうした本題とは関係があるようなないような蘊蓄や雑談が多すぎて、たちまちそちらに気を取られてしまう。たとえば、小説の最後の部分は、このような感じである。
君は幸せだね、ヴッツ君、私が——私がアウエンタールへ行って、草におおわれた君のお墓を探しだし、君のお墓のなかに埋もれていた夜の蝶つまり蛾の蛹たちが翅を生やしてなかから這いだすのではないかと、また、君のお墓があちこち穴をあける蚯蚓たちやのろのろ歩く蝸牛たちやぐるぐる回る蟻たちやしきりに齧る芋虫たちの遊山のキャンプと化しているというのに、一方、君は、そうした虫たちよりももっと下の方で、頭をクッションならぬ鉋屑の上にじっと置いたまま横たわり、君の柩の板や亜麻布の被いが膠着してしまった君の眼を通して陽光が愛撫するように射しこんでくることないのではないかと考えて心を痛めるとき——君は幸せだね、私がそんなときにこう言えるとは、「彼は、まだこの世に生を享けていたとき、われわれの誰にもまして嬉しげにその生を楽しんだ」と。(95p)
蝶だの蛾だの、蚯蚓や蝸牛だの、柩の板や亜麻布だのといった、綿々と続く細部を追うことなく、この本を読み進めることはできない。同時に、こうした細部を除外して、この本の内容を語ることもできない。絶えず、横道に逸れ続けているような、それでいて大きな流れを感じさせてくれるような、この小説を読み続けていくためには、内容を自分の中に主体的に取り込もうとするのではなく、むしろ文章の流れに身を委ねていくような感覚が必要だ。「つまるところ〜」だとか「結局〜」という圧縮された集約的理解を得ようとすることなく、次々と出てくる逸脱的、拡散的なレトリックやメタファーに積極的に気を取られ、その情景を想像しながら思索的に読んでみる。するとその背後から、パウル自身が感じていたであろう、そして描きたかったであろう、考現学的な社会風刺や、文学や芸術批判、そして人生観のようなものが浮かび上がってくる。いずれにせよ、この小説には、金銭的、物質的な裕福さから生まれる幸福とはまったく異なる、個人の生活とその内面の豊かさから生まれる幸福が、綿々と描かれ続けていて、それはこの小説に限らず、パウルの多くの作品に通底するテーマでもあった。
訳者の岩田行一が解説で指摘しているように、この本で描かれたヴッツ先生という架空の人物の物語は、実はジャン・パウル自身の物語でもある。小説の中の「君」や「彼」を、そのまま語り手としての「私」に置き換えることができる。それはいいかえれば、この小説というものが、何かを描写する事実確認的(コンスタティヴ)なものというよりもむしろ、行為遂行的(パフォーマティヴ)であるということだ。
ここで「確認的」と「遂行的」といっているのは、哲学者ジョン・オースティンの「言語行為論」[1]に由来している。この本の中でオースティンは、人間の言語の中には、事実や状況を「記述」したり「言明」するものだけでなく、全面的もしくは部分的に一つの行為を行うことそのものであるようなものがあると主張した。オースティンはこうした言語を「行為遂行的」と呼び、その事例として、以下のようなものをあげている。
・「私は〜を誓います。」
・「私は〜を〜と命名します。」
・「私は〜を〜に譲ります。」
・「私は〜が〜するほうに賭けます。」
これらはいずれも、当たり前すぎるほどにシンプルなものだが、いずれも、何らかの(真偽が判定できるような)事実を言明しているというよりも、当の行為を行うことそのものである。オースティンはこうした文や発話のことを、「行為」に伴う「遂行する(パフォーム)」ということばにもとづいて、「遂行体」と呼んだ。
その後、この行為遂行性、パフォーマティヴィティという概念は、言語を超えて、さまざまな世界の問題に適用されるようになった。例えばフェミニズム理論家のジュディス・バトラーは、「女性」や「男性」というジェンダーは、生物学的な差異によって与えられたものというよりも、むしろ社会の中でパフォーマティヴに構築されたものであり、だからこそ再構築可能なものであるとした[2]。バトラーのみならず、ジャン=フランソワ・リオタールやジャック・デリダのような哲学者が、ポストモダニズムの文脈で、この概念をさまざまな方向に展開していった。しかしここでは、そうした行為遂行性の理論的展開や、哲学的適用ではなく、(メイカーにとって)より始原的ともいえる、「もの」のパフォーマティヴィティについて考えてみることにしたい。
2012年のTEDxBresselsで、ゾーイ・ラフリンというデザイナー/メイカー/材料工学者が「The Performativity of Matter(ものの行為遂行性)」というタイトルの講演を行った。まず初めに、2005年にロンドン芸術大学のセントラル・セント・マーチンズを卒業した後に出会った(青空と同じように光のレイリー散乱で青く見える)「エアロゲル」を紹介しながら、その時に感じた「材料の詩(Poem of a Material)」について熱く語り始める。実際、このエアロゲルという物質との出会いがきっかけとなって、ラフリンはその後2010年に、ロンドン大学キングス・カレッジの工学部で材料科学の博士号を取得している。

The Performativity of Matter: Zoe Laughlin at TEDxBrussels (2012)
https://youtu.be/SrDNwd1mzC4
材料科学の構成要素である元素表に始まり、ミクロからマクロまで、イームズ夫妻による「Powers of Ten」のようなスケールの話、ジェットエンジンのタービンブレードに用いられているスーパーアロイと呼ばれる超耐熱合金、今では身近になった熱すると元の形に戻る形状記憶合金、曲げると音のでるクリスピーでクランチーな金属、髪の毛よりも細い銅の針金、ダイアモンドの次に硬いセラミック、そして最後に液体窒素で冷やした超伝導体の上で浮く磁石など、まさに物質が持つ奇妙な、そして印象的な振る舞い(行為)の数々を、ものに対する情熱と愛情溢れるプレゼンテーションで披露してくれた。
フランク自身は、講演タイトルの「パフォーマティヴィティ」については何も語ってはいないが、ここで披露されたさまざまなものの振る舞いは、オースティンのいう言語の「行為遂行性」に対応するものだ。物質には、講演の最初に提示された周期表のように、材料の構造や性質を示す「事実確認的」な属性もあるが、それだけでなく、広く物性とも呼ばれる多様な性質があり、それらの複合作用によって、そのもの自体が持つ「遂行性」が出現する。
オースティンの示した言語の遂行性にせよ、フランクが実演してくれた物質の遂行性にせよ、その本質は、言語や物質が行った行為そのものにあるのではない。言語を用いて誓ったり、命名したり、譲ったり、賭ける時に、その行為そのものだけを指しているのであれば、それはそうした行為の事実を確認していることに過ぎないし、その真偽を問うこともできる。そうした意味で、確認性と遂行性は、明確に分けられるものというよりも、常にカップリングしている。さらにパフォーマティヴィティは、言語や物質とそれを受け取る対象との間で生まれる、協働的な出来事でもある。「ものにつくられるものづくり」や存在論的デザインを、人間とは反対側から見た時のように、それは言語やものが一方的に行う行為のことではなく、それが人や事物に与える影響と、そこから生まれる行為の遂行こそが重要になる。それは広い意味での、そして本質的な意味での「機能(ファンクション)」と呼ぶべきものだろう。ここで機能とは、対象の仕様や属性のことではなく、その対象が置かれた状況や文脈における、外部との発展的な関わり合いのことを意味している。そんな行為遂行的な機能の代表例は、即興演奏家のデレク・ベイリーが引用している、人間の手の敏活な運動に代表される身体的行為を引き起こす、クルト・ザックスの「器楽的衝動」[3]である。
ある演奏家の即興演奏の基礎をなしている特色、なにを演奏していてもみてとれる特色のひとつは、この器楽的衝動をいかに利用しているか、あるいはそれに反撥しているか、というところにあるだろう。だからこそこの衝動をつくりだすと同時にその受容器でもある楽器というものが、演奏家が音楽をひき出してくる源泉のなかでももっとも重要な、唯一のファクターとなるのだ。(207p)

Derek Bailey Solo – London 1985
https://youtu.be/R71dPy1mvVA
間主観的、相互作用的なパフォーマティヴィティの、もうひとつの重要な特徴は、それが『陽気なヴッツ先生』のテキストのように、そして物質としてのモノのように「要約することができない」ということだ。ものごとの要約とは、対象を事実確認的に簡略化することである。だから、要約にはある種の正しさが求められるし、そうでないものは捨て去られてしまいがちだ。
『陽気なヴッツ先生』の紹介文にある「有名な本の題名だけを拝借しては勝手に著述し、それをわが蔵書の棚に並べて満足感にひたりこむ」という要約にも、確かに何らかのパフォーマティヴィティはある。それだけで、例えばポーランドの作家、スタニスワフ・レムの『完全な真空』(架空の書物の書評集)や『虚数』(架空の書物の序文集)のように、書物のタイトルと内容の虚構性や不確定性という属性を介した、さまざまな方向への妄想が広がっていく。しかしそうした要約からの連想だけでは、先に述べたヴッツ先生=ジャン・パウル自身の生の幸福は伝わってはこない。『陽気なヴッツ先生』という小説が持つパフォーマティヴィティの多くは、(最初に引用したような)物語に直接関係があるようなないような、蘊蓄や雑談といった(読みにくいともいえる)部分にある。
講演の時に取り上げた「ユーモア」も、そうした、ものごとの「要約できない」部分に宿っている。逆の言い方をすれば、ユーモアとは要約できない何ものかである。川上賢治の「珍道具」の数々も、その素材や属性などから、分析的に理解することはできない。「顔中サングラス」「つま先傘」「横寝用メガネ」「ラーメン用ロングヘアストッパー」といった名前や機能だけで、そのユーモアを説明することはできない(名付けることとは、名前による要約に他ならないが、逆に名前だけからヴッツ先生のように勝手にモノをつくったら面白いかもしれない)。珍道具のユーモアは、ヴッツ先生同様に、「つま先傘」の柄や、「ラーメン用ロングヘアストッパー」の襞のように、そのもの自体が持ってはいるが、本筋ではない細部に宿っている。ラフリンが紹介した物質自体のパフォーマティヴィティが、その元素名や化学的構造のような、辞書的情報では伝わらないのと同じである。
ユーモアも、パフォーマティヴィティの一種である、しかもそれはパウルがいうように、悟性(理解)を打ち砕く破壊作用を持っている。ユーモアにとって重要なのは、それ自体が面白いかどうかということではない。ユーモアはむしろ、そのある種の「まじめさ」によって、自分とその周囲が含んでいる矛盾(例えばエアロックの場合はCOVID-19の状況)に光を当て、不可能な事柄(例えば人と人が接しないこと)にも目を向けながら、根拠のないあらゆるドグマを排除しようとする懐疑主義の一種である(それを川上賢治は「逆理のテーゼ」と呼んだ)。だからきっと、ユーモアは(ロックダウンのような)ドグマによってもたらされた悲劇からの、サバイバルにも必要なのだ。
『陽気なヴッツ先生』でパウルが描こうとした、外的な成功なしでもあり得る、ひとつの幸福な生とは、要約できない生である。肩書きや立場といった、存在の要約なしに成立するような生である(肩書きのない人間になる、ということは、要約できない人間になる、ということだ)。パウルが目指した作家とは、肩書きとしての作家ではなく、パンのためだけに書くのでもない一人の人間の、還元できない生そのものであった。メイカーがめざすものづくりも、おそらくはパンのためだけにつくるのではない、生としてのものづくりであるだろう。
エットレ・ソットサス『定理にもとづいたデザイン』と「“Carlton” Room Divider」(1981)
メンフィスのアイコンであるトーテム型の間仕切り「カールトン」。この作品は、仕切り、本棚、チェストを組み合わせたもので、従来の家具の形に疑問を投げかけています。MDF(中密度繊維板)と安価なプラスチックラミネートで作られたこの作品は、ハイエンド市場向けで、精巧なハンドメイドです。鮮やかな色彩や、立体と空洞のランダムな組み合わせは、前衛的な絵画や彫刻を思わせます。しかし、その外観の下には、現実の正三角形と暗黙の正三角形からなる、完全に論理的な構造システムが存在しています。傾斜した棚板は、一見すると直感に反していますが、直立した棚板ではよく倒れてしまう本を収納することができます。この仕切りは、両手を広げてユーザーを迎え入れるロボット、たくさんの腕を持つヒンドゥー教の女神、あるいは自らが作った混沌の上に立つ勝利の女神など、さまざまな解釈が可能です。(メトロポリタン美術館)
イタリアの建築家、デザイナーのエットレ・ソットサスは、「定理にもとづいたデザイン」というエッセイで、このようなことを言っている。
だから、笑顔を生み出すためだけにデザインすることだってありうるのだと思う。私たちが度々溺れてしまう声なき沈黙に立ち向かうために、デザインすることだってあるはずだ。
(中略)
必ずしも同じ椅子や、ソファーや、歯ブラシを1万本生産することを目指さなくても、デザインすることだってあってもよい。
デザインの定理を追求するためにデザインすることがあってもよい。
(中略)
実に複雑でなおかつ魅力的なデザインの定理を思い浮かべながら、考えたりデザインしたりすること、すなわち存在意義を定理づけること。その行為を、私は“定理に基づいたデザインをする、もしくは定理に基づいたデザインを思索する”と呼んでいる。
デザインの定理のことで頭がいっぱいになっていると、しばし、ワードロープやテーブル、バイク、ドアなどは、人間の力を増強させる補助器具のようなモノとしてのみのためにデザインされていないはずだと思い直すことがある。敵を殺すためだけの弓矢のデザインではないだろうし、スープをためるためだけの容器のデザインではないだろう。洗ってあるリネンをしまうためだけのチェストでのデザインでもないだろう。
(中略)
デザインの背後にはいつもほんの一瞬の沈黙が隠されている。…(25−26pp)
ソットサスがいうデザインの定理とは、デザインの逆理である。ものには今見えているもの、気づいていること以外にも、たくさんのはたらきがある。ソットサスの「カールトン」のように、ものには、何らかの目的をもった振る舞い以外のものが、たくさん含まれていて、それらを除外すること、つまり要約することはできない。ものをつくるとき、そして使う時には、そうしたもの自身が有している、要約することのできない、本題とは関係があるようなないような蘊蓄や雑談のパフォーマティヴィティを、丘歩きのように何度も体験することができる。そんな「要約できないもののパフォーマティヴィティ」にこそ、大文字の製品づくりや大量生産の商品づくりにはない、メイカー個人による持続的ものづくりの、大切な特徴があるのではないだろうか。
(続く)
[1]ジョン・オースティン『言語と行為 — いかにして言葉でものごとを行うか』 飯野勝己訳,講談社学術文庫(2019)
[2]ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル 新装版 ―フェミニズムとアイデンティティの攪乱― 』竹村和子訳,青土社(2018)
[3]デレク・ベイリー『インプロヴィゼーション ― 即興演奏の彼方へ』 竹田賢一・斉藤栄一・木幡和枝訳,工作舎(1981)
[4]エットレ・ソットサス『定理に基づいたデザイン』Shiodome italiaクリエイティヴ・センター(2006)